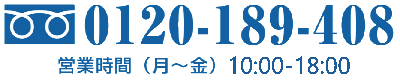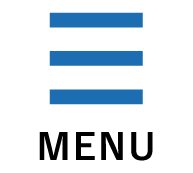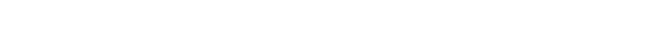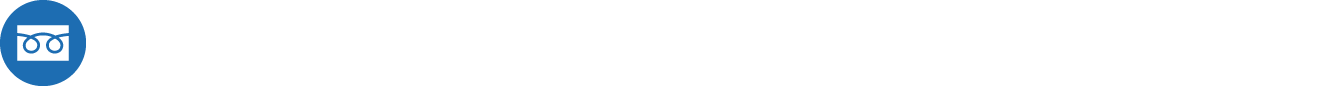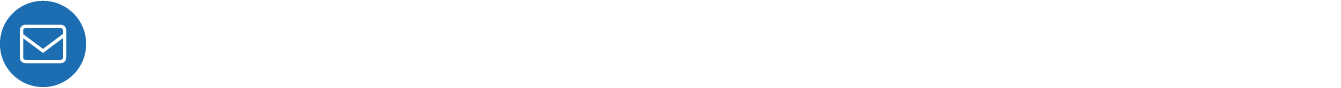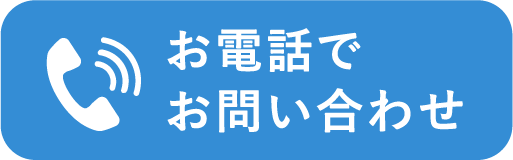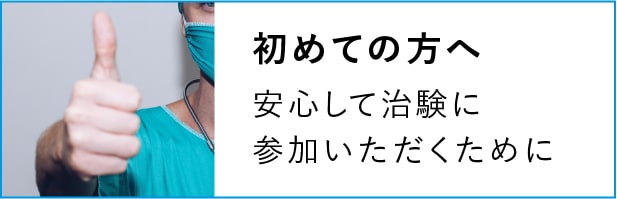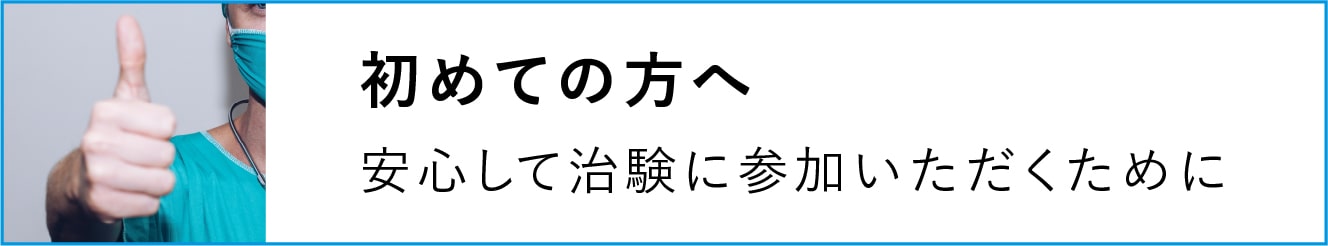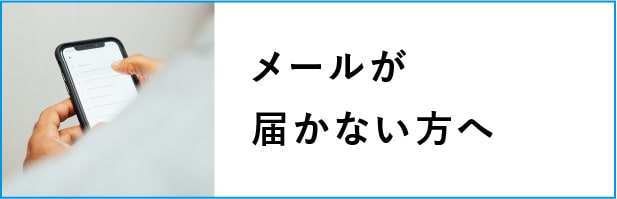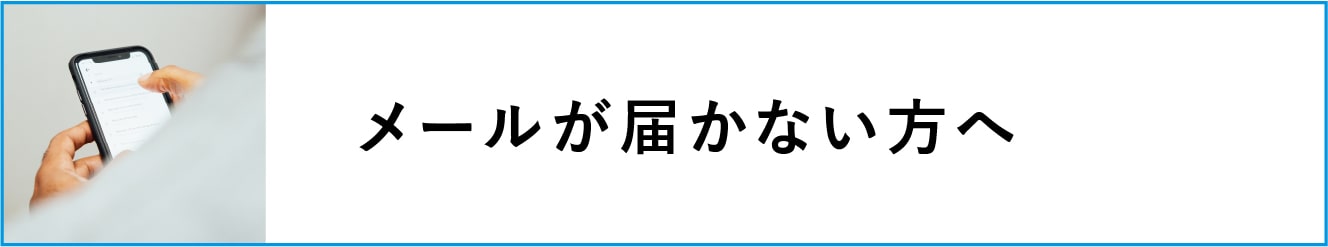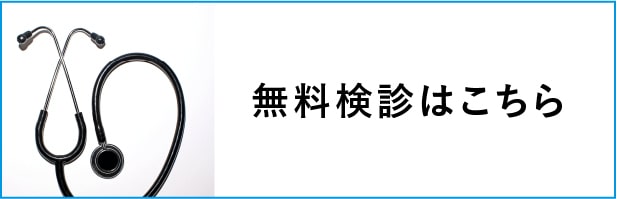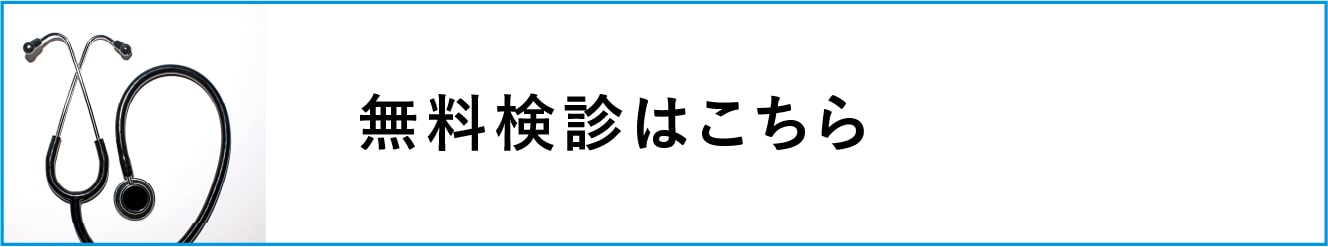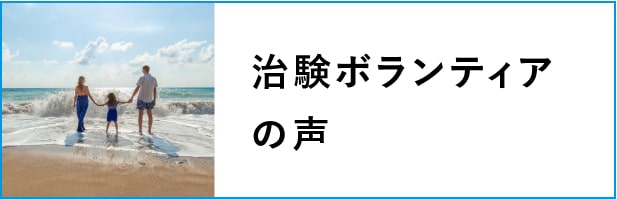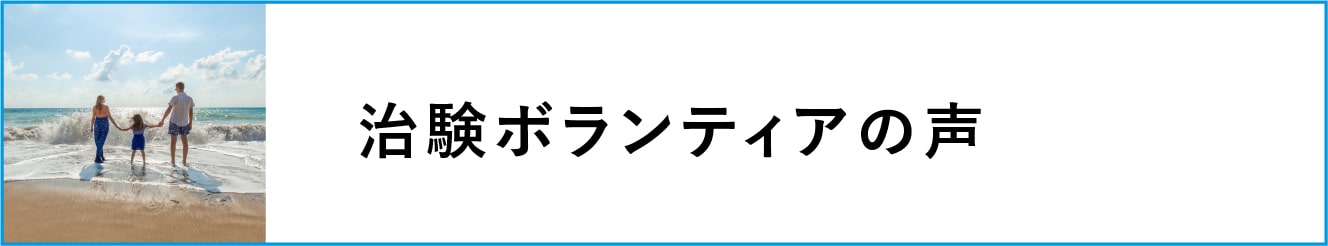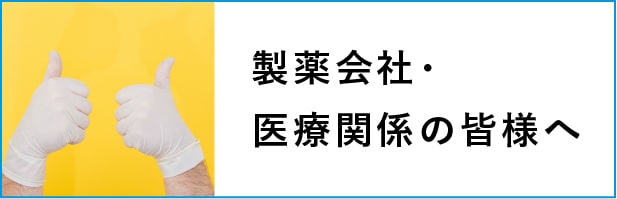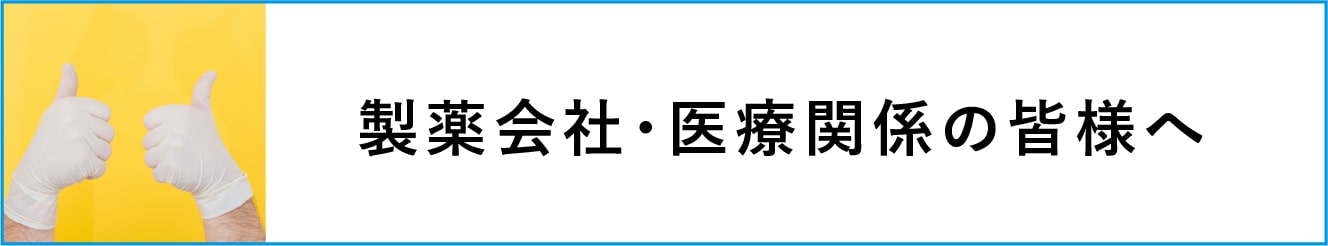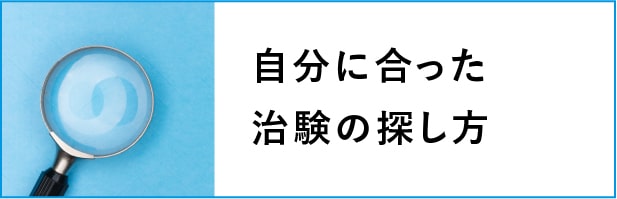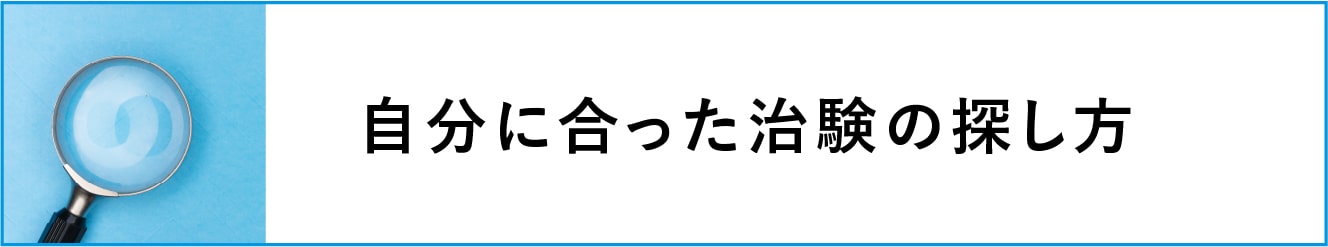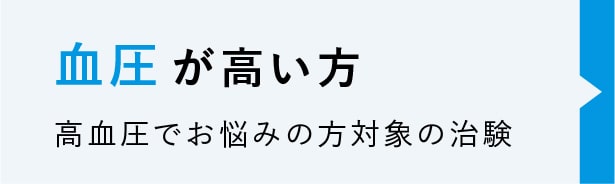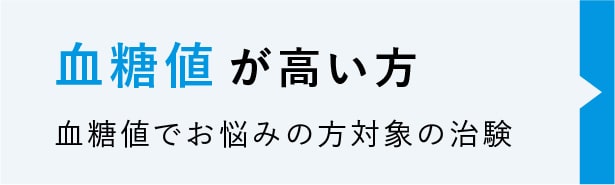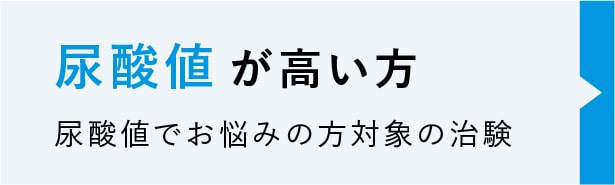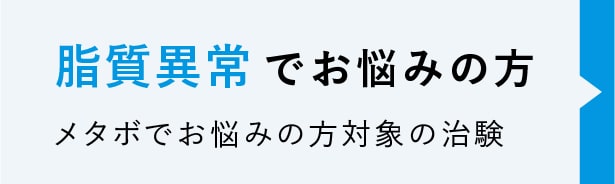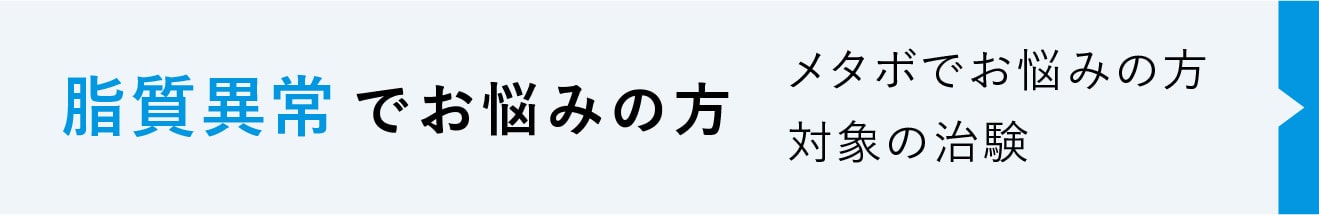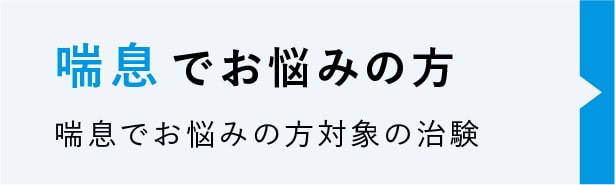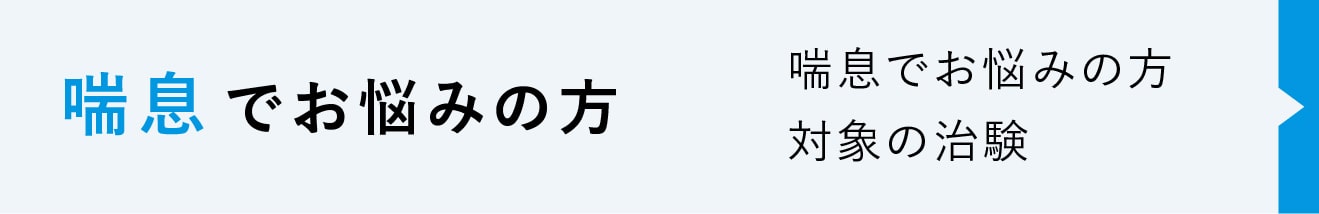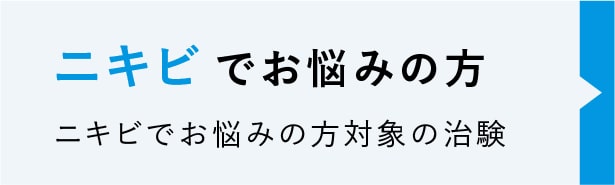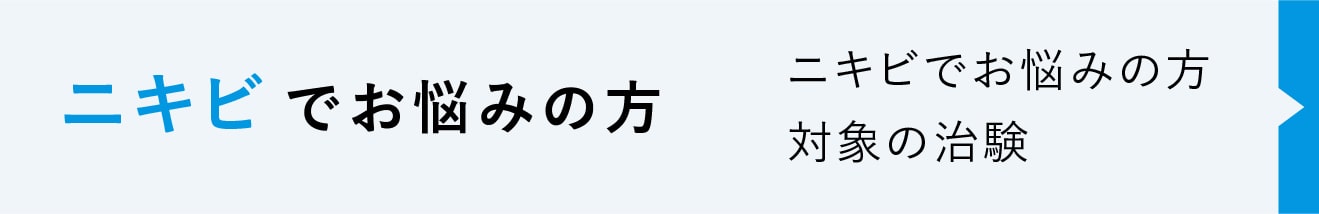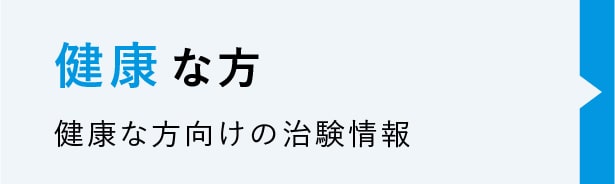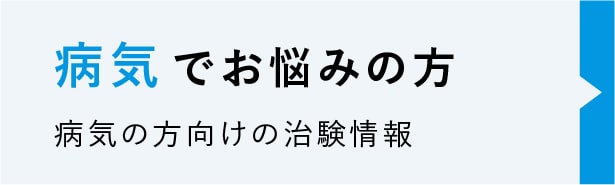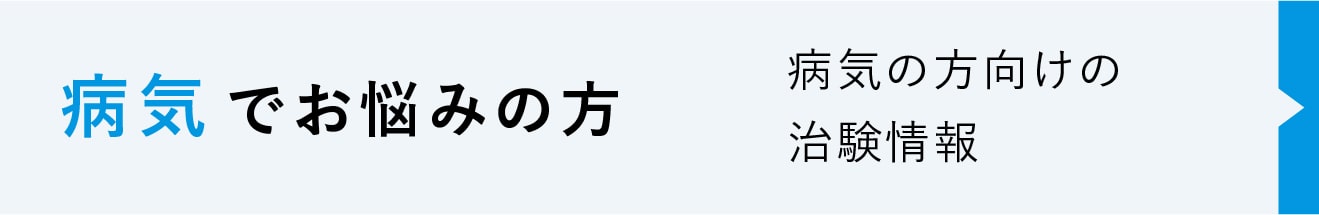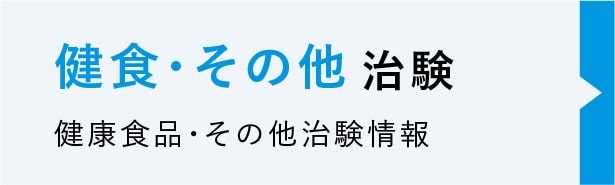【掲載日】2021/08/17 【最終更新日】2023/05/18
糖尿病は治る?(寛解する?)食事や運動療法でどこまで治すことができる?
糖尿病は治る?
糖尿病とは「血糖値がとても上がりやすい体質」に変わった状態を指すため、糖尿病を完治することは難しく、状態を「緩和」または「寛解」することができます。
2型糖尿病は寛解することも
2型糖尿病は、暴飲暴食や運動不足、肥満などの不摂生な生活習慣を継続することで、インスリンを多量に出し続ける状態が続くと、インスリンを生成する膵臓内の細胞『ランゲルハンス島β細胞』が疲弊してしまい、インスリン分泌力の機能低下に伴い血糖値を下げることができなくなる病気です。
そのため、食事療法や運動療法など、日々の生活習慣を改善することで膵臓の負担を軽減し、ランゲルハンス島β細胞が回復することで寛解できる場合もあります。
しかし、一度疲弊したランゲルハンス島は疲弊しやすくなっているため、不健康な生活習慣に戻ってしまうと、再び糖尿病は悪化していきます。
1型糖尿病は完治が難しい
1型糖尿病は遺伝や生まれつきの体質により、膵臓のインスリンを作り出す細胞であるランゲルハンス島β細胞が機能しないことで発症します。
機能しないランゲルハンス島β細胞を治す治療法は見つかっておらず、インスリン注射などによる外的な補充により、健康な身体の状態を維持することはできます。
思い切り痩せたら治るって本当?
ダイエットなどで大幅な減量に成功し、血糖値が下がったので糖尿病が完治した、というのは誤りです。
肥満体型の方はインスリンが効きにくい状態のため、適度な運動で脂肪を減らし、筋肉量が増えることでインスリンが効きやすい状態の身体になります。ですが、この状態はあくまで寛解状態であり、完治には至りません。再度不摂生な生活習慣に戻ったり、暴飲暴食をすることで糖尿病は次第に悪化していきます。
糖尿病を放置した場合のリスク
悪化の恐れ
糖尿病による身体的な影響は、インスリンの欠乏や血糖値の上昇から始まり、目に見える症状は発症から時間が経過してから発覚するため、糖尿病を発症していると気づかずに進行している場合が多い病気です。糖尿病に気づかず進行してしまう理由は大きく2つあります。
1つ目は、インスリンを分泌する膵臓の機能が加齢によって徐々に落ちるためです。インスリンとは、主に食事から摂取されたブドウ糖をエネルギーにかえるためのホルモンであり、インスリンが十分に分泌されない、あるいはその作用が正常に発揮されないと、ブドウ糖をエネルギーに変えることができません。その結果、血液中のブドウ糖が体内に蓄積されることで高血糖状態を招いてしまいます。高血糖状態では、諸臓器、細胞は、十分なエネルギー供給、燃焼が行われず、機能不全に陥ります。
2つ目は、高血糖状態が継続するほど、膵臓のインスリン分泌機能そのものが疲弊してしまいます。糖尿病になったからといって身体的な異変が見られず、軽視し治療を怠ることで高血糖状態が長期間に渡ると、さらに高血糖を助長するという悪循環を招いてしまいます。
合併症の発生
糖尿病が進行すると、さまざまな合併症が生じます。
- 糖尿病網膜症
- 糖尿病腎症
- 糖尿病神経障害
- 脳梗塞
- 狭心症・心筋梗塞
- 閉塞性動脈硬化症
- 糖尿病性潰瘍・壊疽
- 歯周病
- 認知症
- 糖尿病性ケトアシドーシス
- 高浸透圧高血糖症候群
- 感染症 など
糖尿病には生活習慣の改善が重要
食事療法
糖尿病は適正な体重や接種カロリーをコントロールするためにも、適切な食事管理が大切です。食事をする際に、以下のような点に注意しながら食事をしましょう。
- 摂取カロリー・・・必要以上に食べすぎていないか
- 栄養素バランス・・・偏食せず、さまざまな食材をバランスよく食べているか
- 食事時間・・・朝食を抜いたり、就寝直前や深夜に食事をしていないか
- 食事の順序・・・野菜から先に食べるように心がけているか(ベジファースト)
- 食事にかける時間・・・よく咀嚼(そしゃく)し、早食いをしていないか
運動療法
適度な運動は、インスリンによる糖の調整を効きやすくし、糖を消費しやすい体質となります。
インスリンの効きやすさのことを『インスリン感受性』と呼びますが、インスリン感受性が高い人は、少量のインスリンでも血糖値が下がりやすく、逆に低い人は血糖値を下げるために多量のインスリンが必要となります。
インスリン感受性を高めるためには、継続的な運動療法が重要です。
激しい運動をしても、一時的な運動だと効果は3日以内に低下し、1週間で消失するといわれています。そのため、理想としては適度な運動を週3~5日以上継続することが望ましいです。
例えば、通勤時に到着駅一つ手前の駅で降りて歩く、帰宅時にも同様に一つ手前の駅で降りて歩くだけでも週5日継続することで十分な運動となります。
糖尿病の基礎知識一覧
- 糖尿病の予防は食生活と運動での体質改善から~すぐに始められる予防法ご紹介~
- インスリンの副作用とは?血糖値を下げる仕組みや注意点を解説
- 高血糖とは?血糖値が高いときの原因・症状・治療について解説
- 糖尿病は治る?(寛解する?)食事や運動療法でどこまで治すことができる?
- 1型糖尿病とは?原因や症状は?治療方法や食事について
- 糖尿病の食事療法-悪化させるダメな食べ物や良い食べ物を解説
- 糖尿病とは?症状や治療法について解説
- 糖尿病の原因
- 糖尿病の診断基準とは?検査方法や診断までの流れを解説
- 糖尿病の合併症
- 糖尿病の治療方法とは?薬の種類や適切な食事方法を解説
- 糖尿病の治療薬
- 糖尿病の治療費
- 糖尿病の最新治療薬とは?糖尿病を治すポイントと治療の流れ
人気の記事
治験ボランティア登録はこちら
その他の病気の基礎知識を見る
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- PMS(月経前症候群)
- あせも
- アトピー性皮膚炎
- アルツハイマー型認知症
- アレルギー
- インフルエンザ
- ウイルス
- おたふく風邪
- がん
- クラミジア
- コレステロール
- しびれ
- とびひ
- ドライアイ
- ニキビ
- はしか
- メタボリックシンドローム
- めまい
- リウマチ
- 不妊症
- 体重減少
- 便秘
- 前立腺肥大症
- 口内炎
- 咳
- 喉の渇き
- 夏バテ
- 子宮内膜症
- 子宮外妊娠
- 子宮筋腫
- 心筋梗塞
- 手足口病
- 新型コロナウィルス
- 更年期障害
- 気管支喘息
- 水疱瘡
- 水虫
- 熱中症
- 物忘れ
- 生活習慣病
- 疲労
- 痛風
- 糖尿病
- 耳鳴り
- 肝硬変
- 脂質異常症(高脂血症)
- 逆流性食道炎
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)
- 関節痛
- 難聴
- 頭痛
- 頻尿
- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)
- 高中性脂肪血症
- 高尿酸血症(痛風)
- 高血圧
- 鬱病(うつ病)