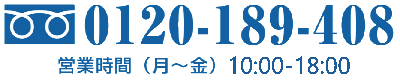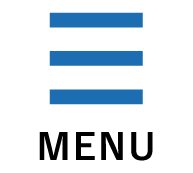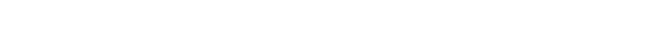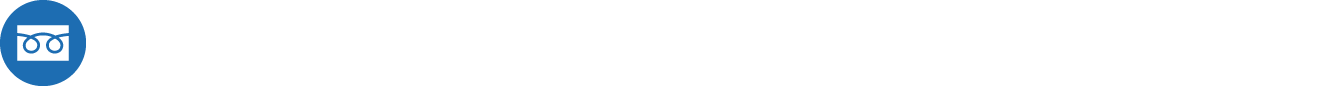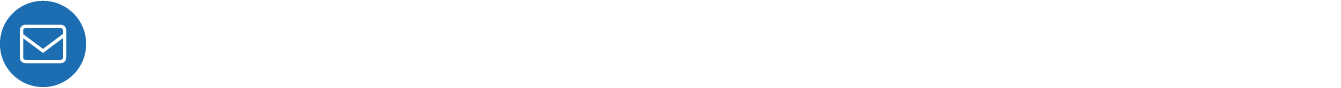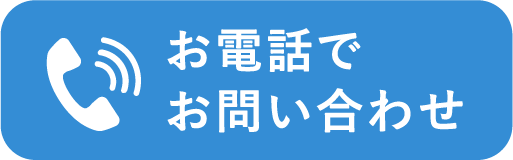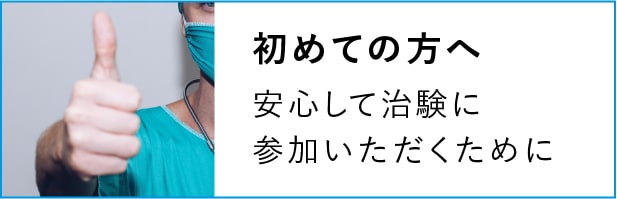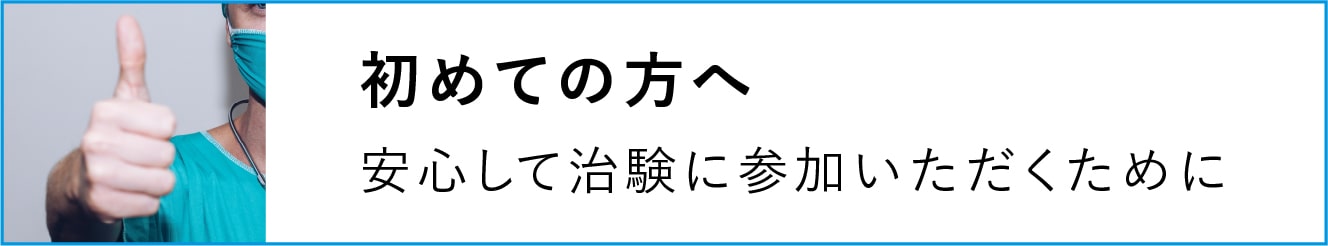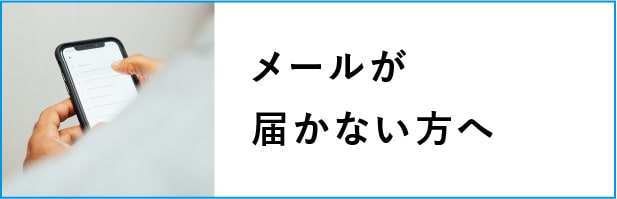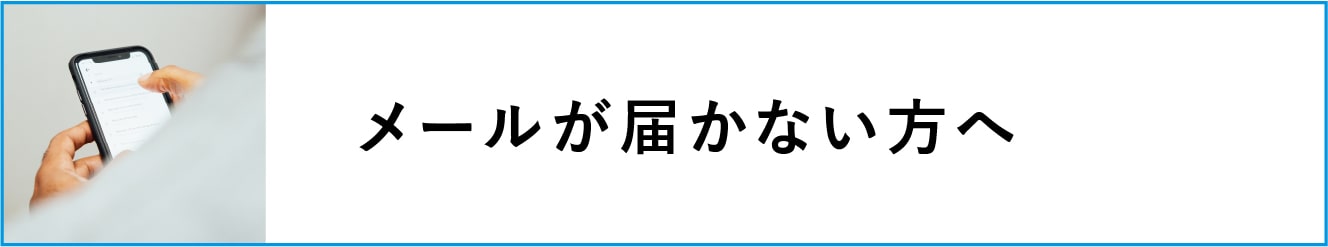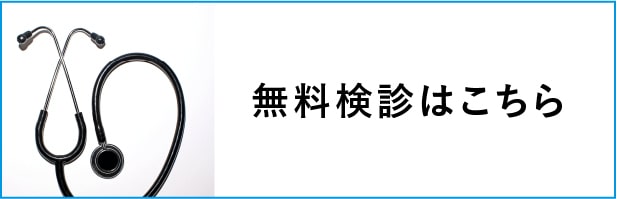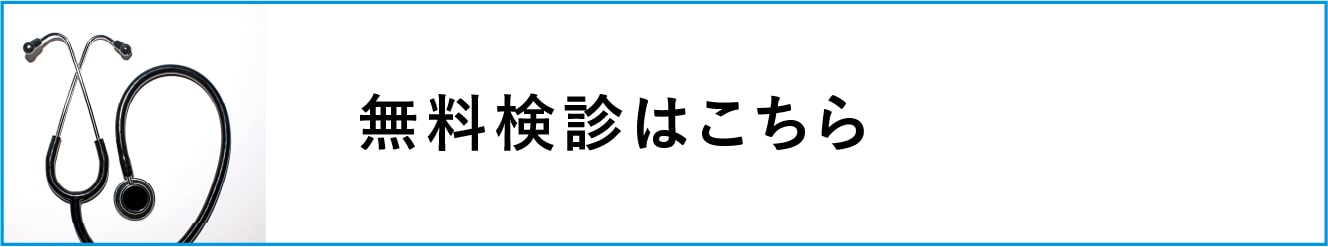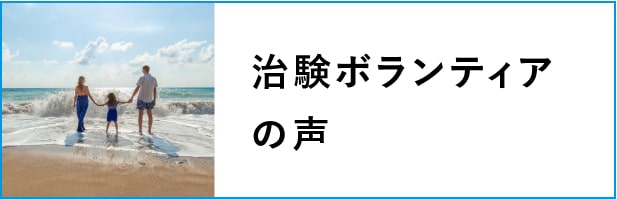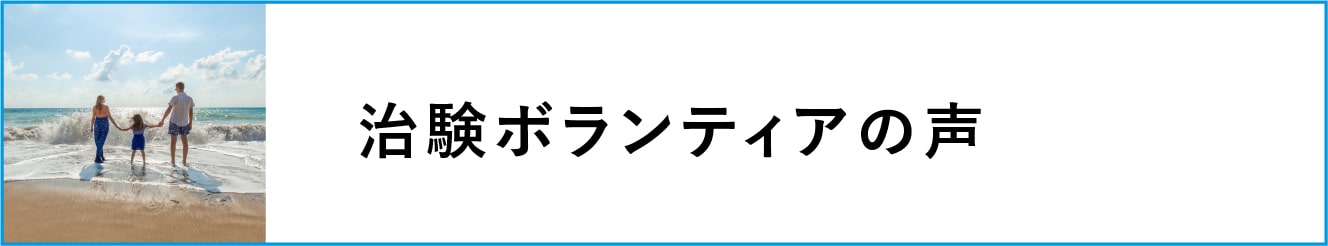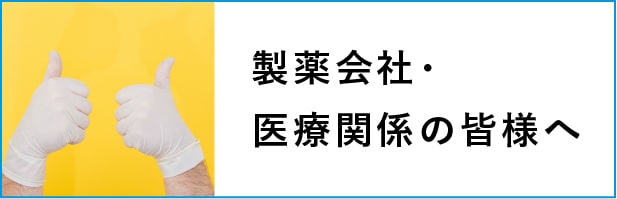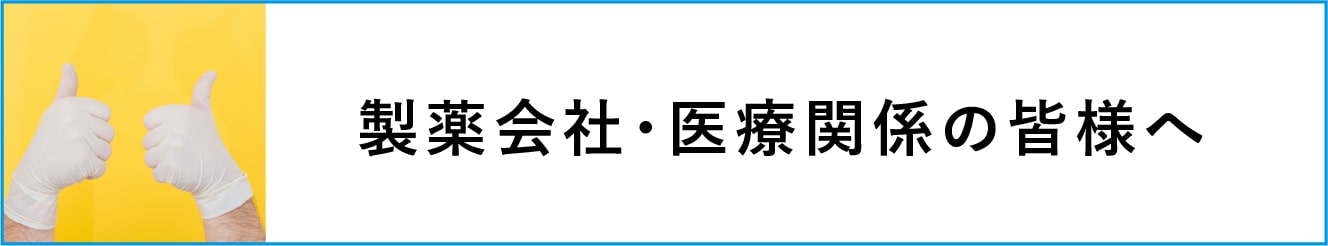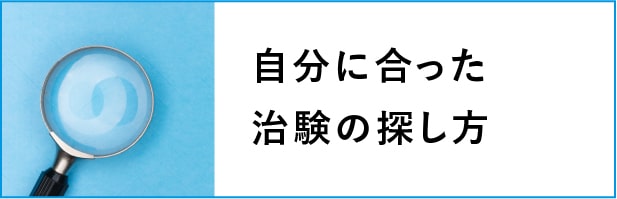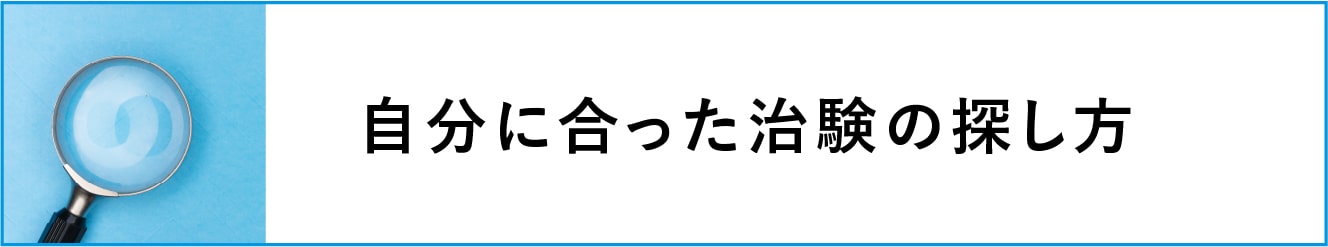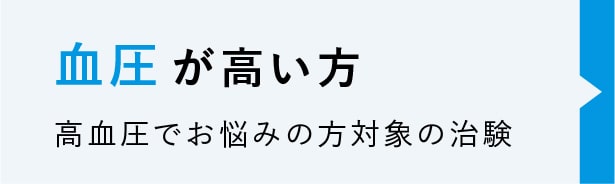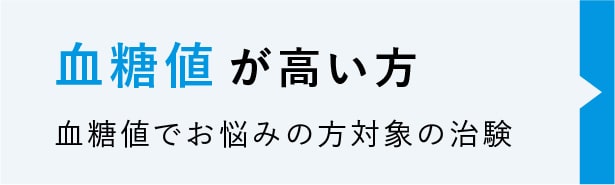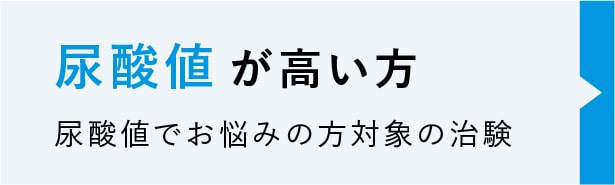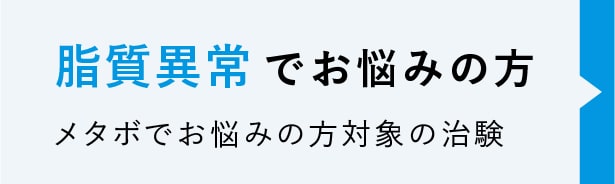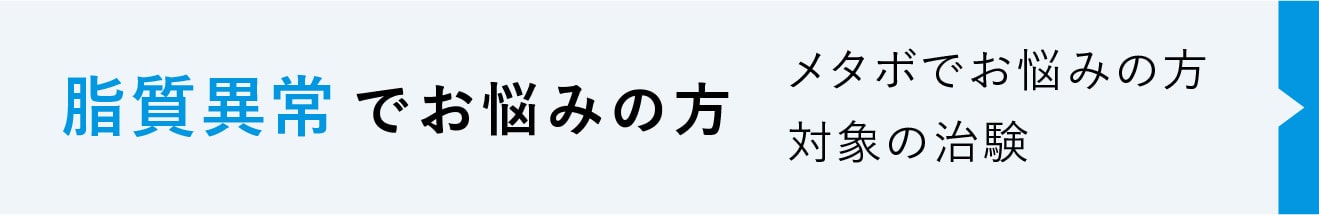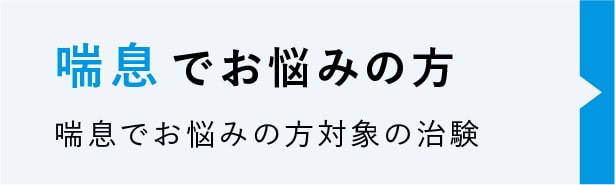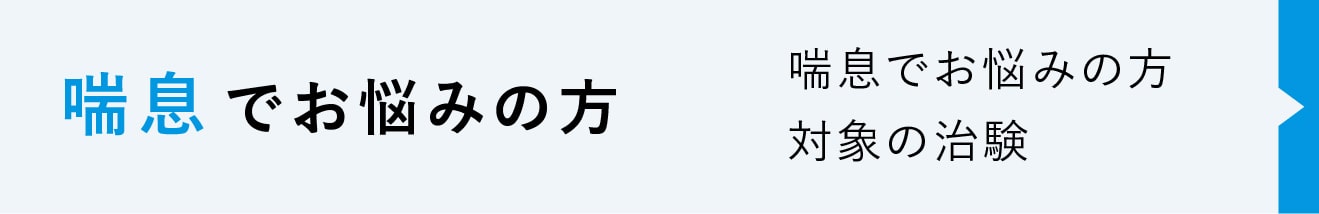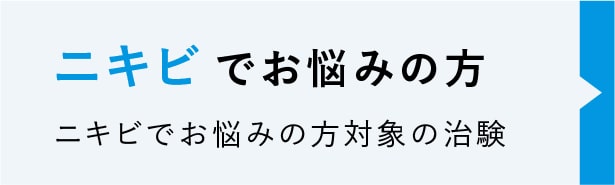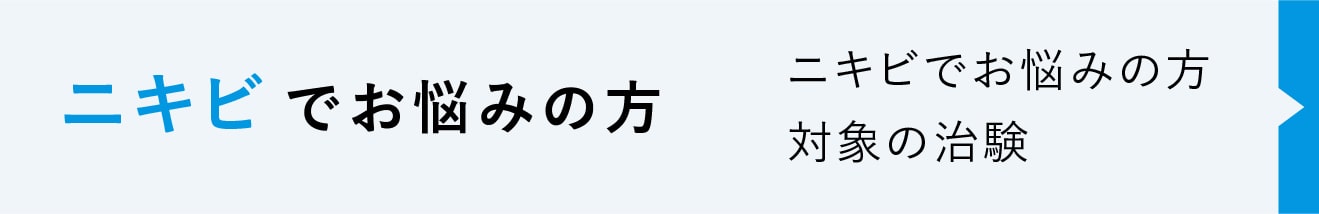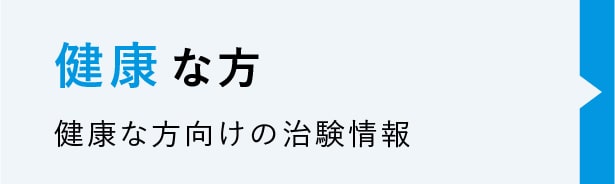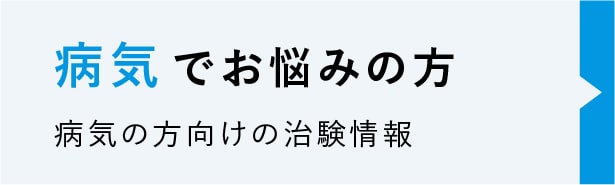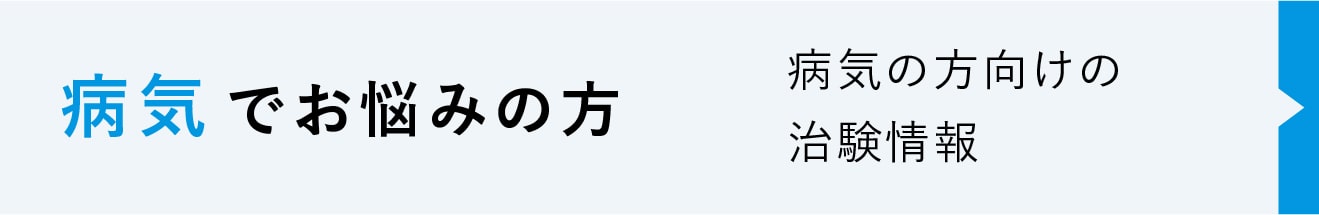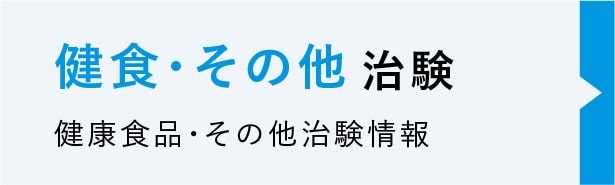【掲載日】2022/04/06 【最終更新日】2023/06/21
頭痛の原因とは?予防法から対処法まで解説

-
監修者
内科医・公衆衛生医師
成田亜希子医師
頭痛が起きる原因とは?
日本人の約3,000万人が「頭痛持ち」と呼ばれています。
多くの方が普段感じているような頭痛の多くは、他の病気が原因ではない「一次性頭痛」によるものです。一次性頭痛はストレスや生活習慣の乱れ、普段と異なる環境や緊張などがあると感じやすくなるのが特徴であり片頭痛や緊張型頭痛などが挙げられます。
1.片頭痛
片頭痛は、頭の片側または両側がズキズキと脈打つように痛むことが特徴的で、何らかの理由で脳の血管が急激に拡張し、周囲の神経が刺激されることで発生した炎症物質が、さらに血管を拡張することで発症すると考えられています。
片頭痛は男性よりも女性に多くみられ、女性ホルモン(エストロゲン)の減少が原因の1つと考えられています。その他、過眠、睡眠不足、空腹、気圧変化や天候、光や音の強い刺激なども片頭痛を誘引するものとされています。
2.緊張型頭痛
緊張型頭痛は一次性頭痛の中でも最も多い病気であり、圧迫され締め付けられるような痛みが特徴的です。発症理由は側頭部から首、肩に至る筋肉が緊張することで強張ってしまい、血流の低下により筋肉内に老廃物が蓄積され、痛みの原因となるプロスタグランジンと呼ばれる物質などが発生することが原因とされています。
主にPC操作などで長時間同じ姿勢をとり続けている人や、精神的・身体的なストレスを抱えやすい人が緊張状態になりやすいと言われています。
対して、他の病気など、発症理由が明確な頭痛を「二次性頭痛」と呼びます。異常な痛み、意識障害、吐き気や手足など身体の異常が伴う頭痛の場合は、二次性頭痛の可能性があります。
二次性頭痛の主な原因は、頭部外傷、髄膜炎、くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍など、場合によっては命に危険を伴う病気が引き金となっている可能性があります。
頭痛の予防法
1.頭痛発症タイミングの把握
頭痛が起きる際にどのような環境だったかを把握することで、原因となる場面を避けるように意識しましょう。また、女性の場合は女性ホルモンが関与する頭痛もあるため、自身の月経周期を管理し、頭痛が起きそうな時期には激しい運動や無理な労働を避けるように、あらかじめ調整しましょう。
2.生活習慣を整える
睡眠の質の低下や空腹は頭痛を引き起こしやすくするため、適切な睡眠や食事を摂るようにしましょう。なお、睡眠の質を取り戻そうと寝だめや二度寝をすることは、空腹と寝過ぎが重なって片頭痛を重くすることもありますので注意が必要です。
また、緊張型頭痛の人は肩や首がこりやすい長時間のデスクワークなどは避け、適度にストレッチやマッサージをすることが予防につながります。
3.頭痛を誘発するような食品の摂取を控える
ポリフェノールや亜硝酸塩などは血管を拡張させる作用があるため、片頭痛を誘発するといわれています。上記を含むチョコレート、チーズ、ベーコン、赤ワインなどの食品は、摂り過ぎに注意しましょう。
4.長時間同じ姿勢をとらない
筋肉の強張りを避けるため正しい姿勢を心がけ、長時間同じ体勢での作業をしないように注意しましょう。
5.肩、首の血行アップ
肩や首のコリは血流を悪くしますので、簡単にできるストレッチをこまめに行い、首や肩の筋肉の緊張をほぐしましょう。
ストレッチ例
両肩を上げ、脱力しながら落とします。(10~20回程度繰り返す)
左手で頭を軽く押さえ、肩の力を抜いて左へ倒し、反対側も同様に行います。(5~10回程度繰り返す)
イスに浅く腰をかけ、脚を前に伸ばしたまま両肩の力を抜いてゆっくり前屈をします。(5~10回程度繰り返す)
6.枕の高さを調整
自身に合わない枕は横になった状態でも首に負担がかかり、就寝中でも筋肉を緊張させてしまう場合があります。高すぎず、柔らかすぎない自分に合った枕を選ぶことで予防ができます。
頭痛が起きたときの対処法とは?
1.頭部を冷やし、体を温めすぎない
冷たいタオルなどを頭痛がする箇所に当てると、周囲の血管が収縮して痛みを軽減する効果があります。また、血行を良くするために半身浴やストレッチをすることもありますが、緊張型頭痛の人には一定の効果が規定できる一方で片頭痛の人は血管を拡張させてしまい痛みを増長させてしまうこともあるので注意しましょう。
2.周りからの刺激が少ない場所で休息を取る
片頭痛の人は、眩しい光や騒音でも過敏に反応して痛みが増すことがあります。頭痛があるときはできるだけ静かな暗い場所で安静にしましょう。
3.カフェイン飲料を適量飲む
コーヒーや紅茶、日本茶に含まれるカフェインは血管を収縮する作用があり、片頭痛の人は痛み初めに飲むと頭痛を軽減する効果があります。なお、カフェインを過剰摂取してしまうと血管が常時収縮状態となり、摂取を止めた際に反動的に血管が強く拡張するため、逆に頭痛を誘発することもあるので、摂取量は程々にしましょう。
まとめ
頭痛の原因によって、予防や対処法は全く異なります。
頭痛の頻度や箇所、他の身体に異常が無いかなどを細かく分析し、自身の頭痛を正しく理解することが重要です。また、隠れた症状が頭痛を引き起こしている場合もあるので、頭痛が心配な場合は速やかに医療機関に診てもらうことをおすすめいたします。