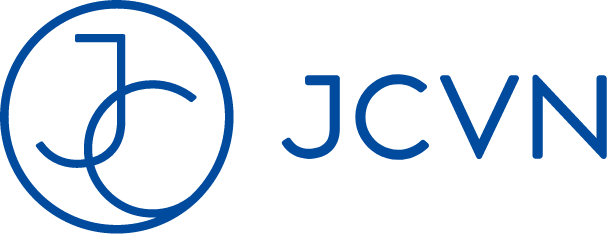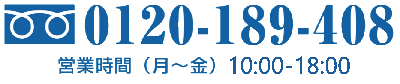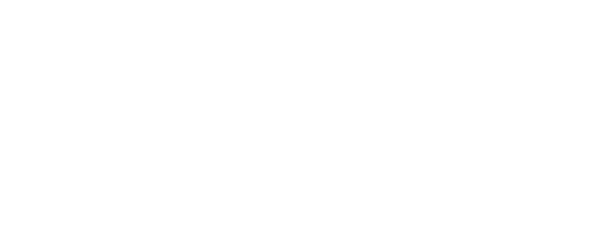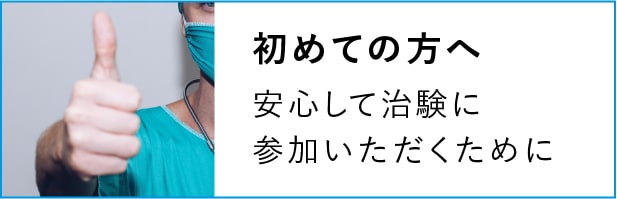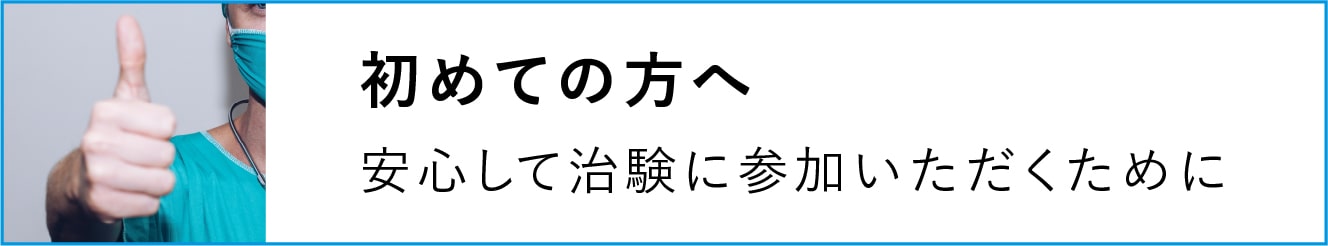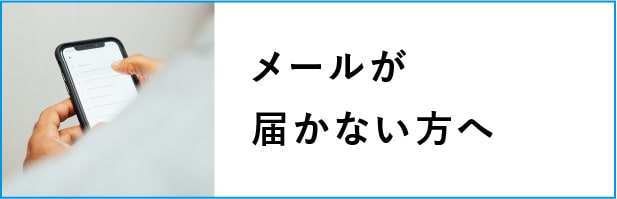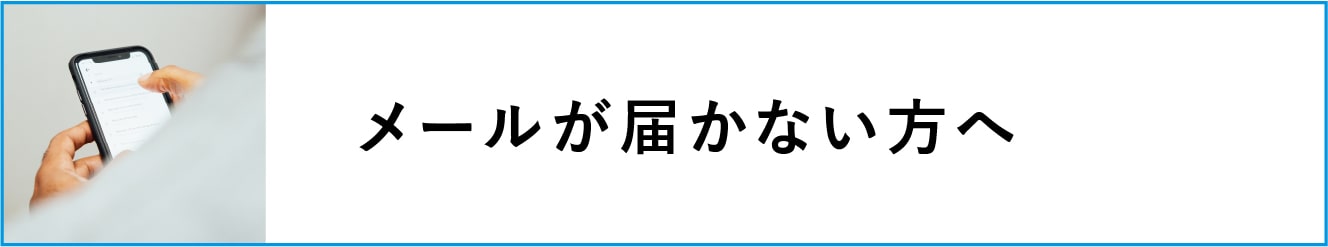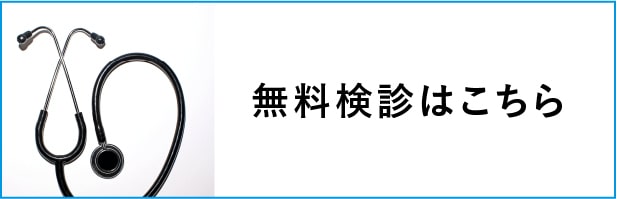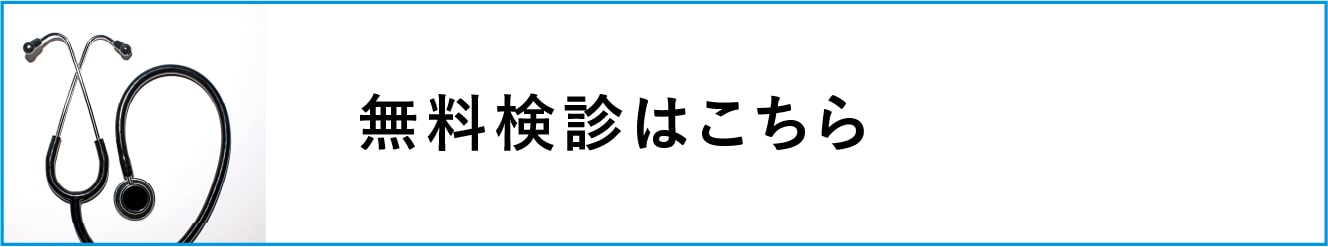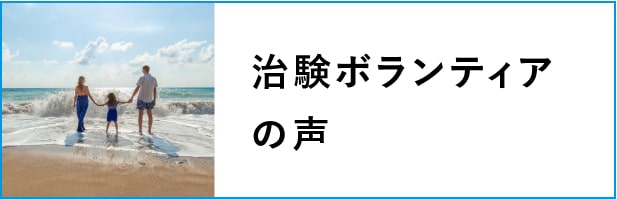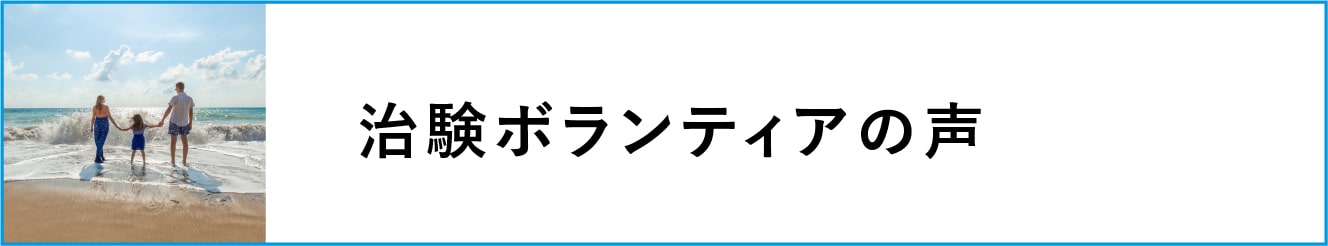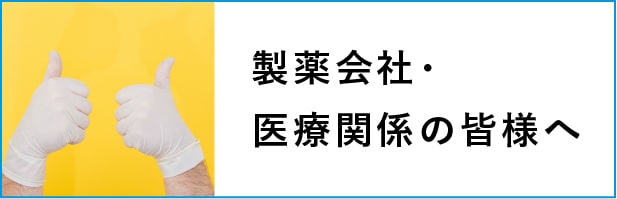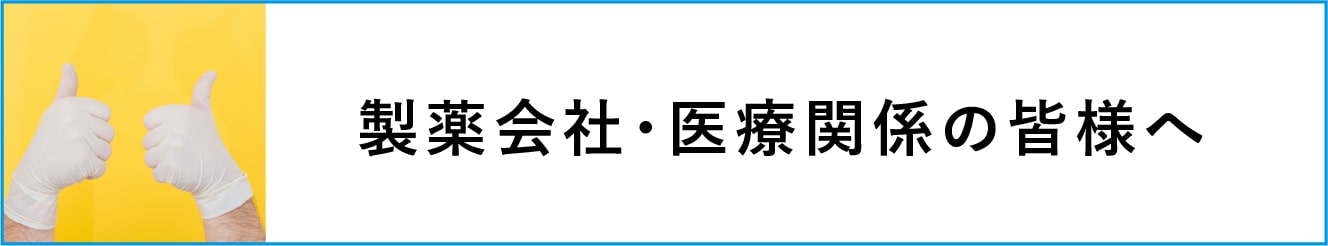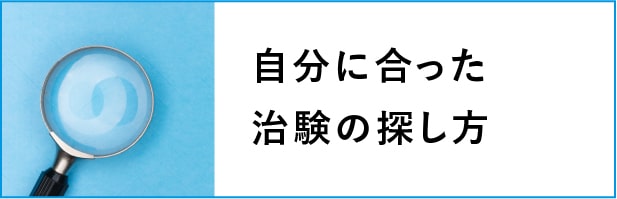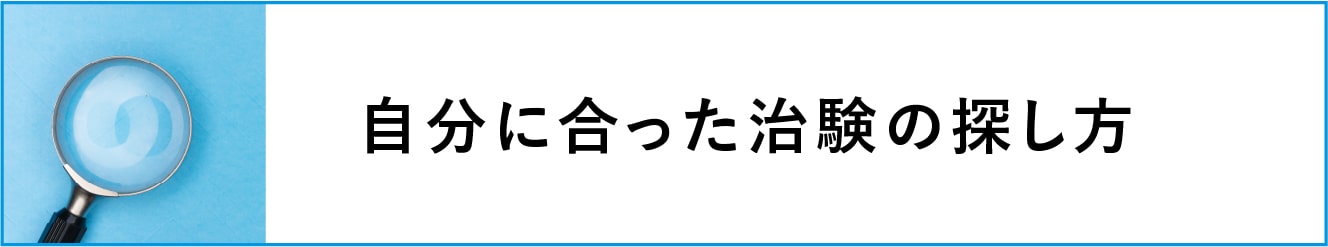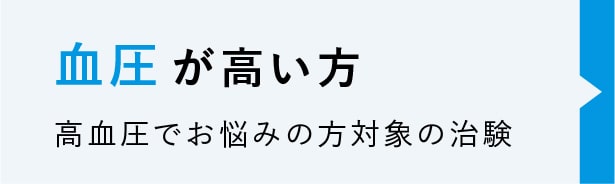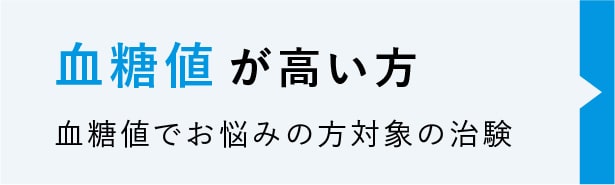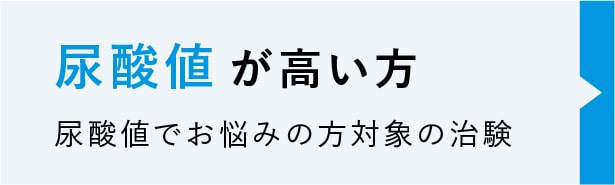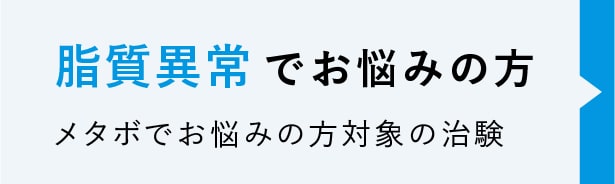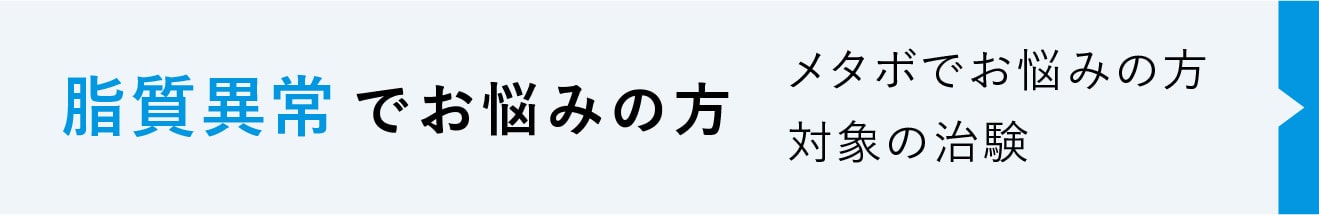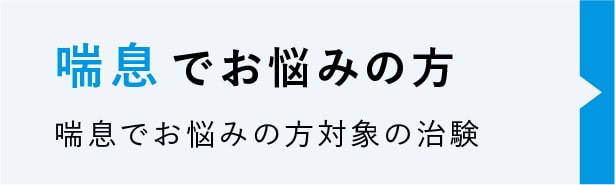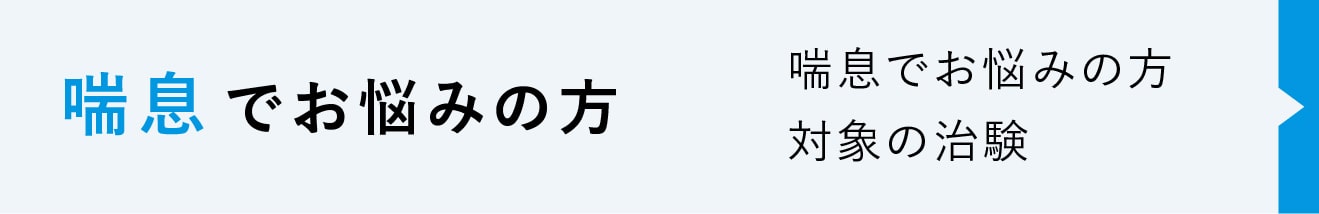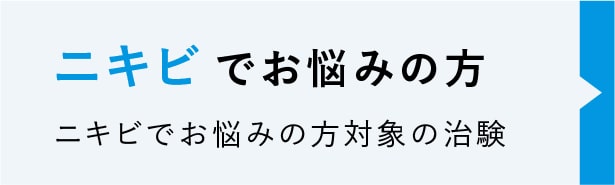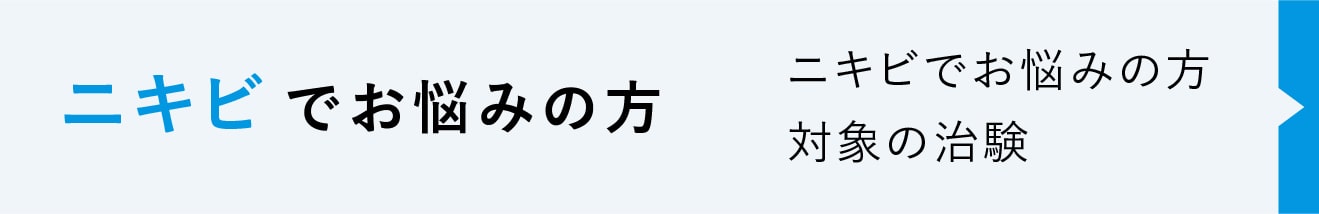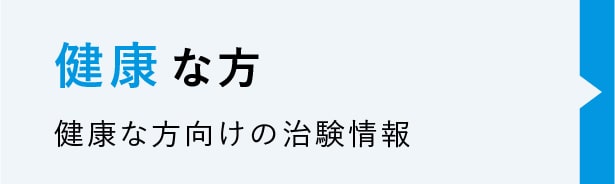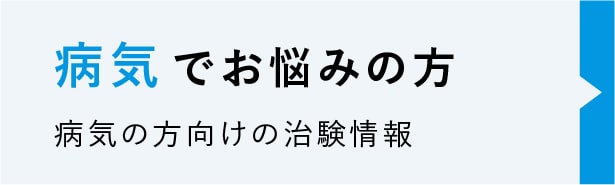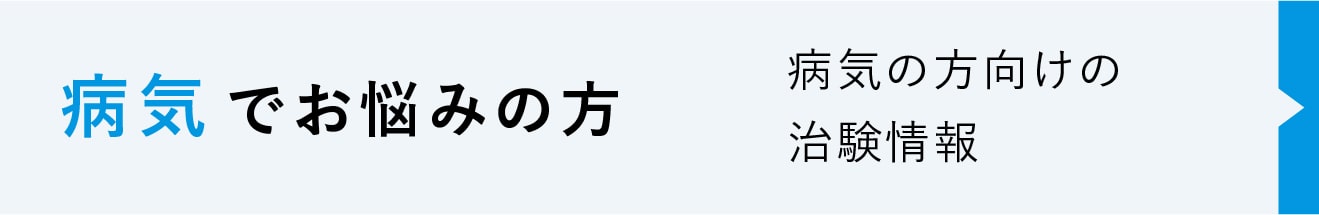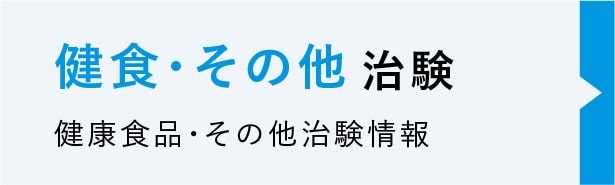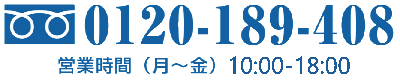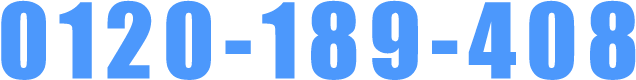【掲載日】2025/08/29
健康食品における臨床試験(治験)とは?目的や役割を徹底解説
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1. 本コラムに掲載されている情報は、記事により薬剤師や医師など医療・健康管理に関する専門資格を有する方による執筆または一部監修を入れ評価検証を行った上で掲載しております。掲載内容については掲載時点での情報をもとに可能な限り正確を期すよう、当社自身でも慎重に確認を行っておりますが、記事によっては執筆者本人の見解を含むものもあり、正確性や最新性あるいは具体的な成果を保証するものではありません。あくまでも読者の皆さまご自身の判断と責任において参考としてご利用ください。また、掲載後の状況変化等により予告なく記事の修正・更新・削除を行う場合があります。
2. 本コラムにおける一般用医薬品に関する情報は、読者や消費者の皆さまが適切な商品選択を行えるよう支援することを目的に作成しているものです。また、当該コラムの主な眼目は「商品」ではなく「成分」にあり、特定商品の広告目的や誘引を企図したものではありません。併せて、特定の医薬品メーカーや販売業者から紹介や販売を目的とした報酬などの対価を受け取っているものでもありません。
3. 本コラムに記載されている商品名やサービス名は、それぞれの提供元または権利者に帰属する商標または登録商標です。
4. 前述の内容に関連して、読者の皆さまに万一何らかの不利益や損害が発生した場合でも、当社はその一切について責任を負いかねます。
5. 本コラムに関する個別のお問合せには一切応じておりませんが事実と異なる誤った記載があった場合はご指摘のご連絡を頂けますと幸いです。
私たちの食生活に欠かせない存在となっている「健康食品」。しかし、その効果や安全性はどのように確かめられているのでしょうか?一部の健康食品では、新薬と同じように「臨床試験(治験)」を行い、身体への作用や効能を確かめるケースもあります。
本コラムでは、健康食品における臨床試験の目的や役割、そして医薬品との違いについて、わかりやすく丁寧に解説していきます。
食品試験とは何?
治験とは、開発された新薬が国から承認を得るために、その安全性や有効性を科学的に証明するための重要なステップですが、開発された健康食品やサプリメントなども同様に安全性や有効性を評価するため、食品試験と呼ばれる臨床試験が実施されています。
私たちの命と健康を支える「食」に関わるからこそ、消費者が安心して食品を選択できる環境が求められます。そのためには、新しく開発された健康食品やサプリメントに対し、食品試験を通じて科学的根拠に基づいた高い信頼性の確保が必要とされています。
食品試験を行う目的
健康食品とは多くの場合、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類を総称する保健機能食品のことを指しています。
特に、「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類を総称した保健機能食品には、いずれも健康の維持または増進に役立つ効能・効果が含まれており、国が定めた基準に則った安全性や機能性を表示しなければなりません。これらのエビデンスを評価するために食品試験が必要となります。
トクホ(特定保健用食品)の場合
トクホ(特定保健用食品)とは、健康の維持や増進に役立つ機能がその食品に含まれていると科学的に根拠として示されている食品です。トクホとして認められるには、その食品を実際に人が摂取した上での試験が必要とされ、有効性や安全性についての科学的根拠を提出しなければなりません。これらのデータをもとに、メーカーなどの事業者が消費者庁に申請し、食品ごとに厳格な審査が行われます。審査を通過すれば「この商品には〇〇を改善する働きがあります」といった具体的な機能性を表示することができます。
消費者庁によって認可された健康表示には、以下のようなものがあります。
●体脂肪・中性脂肪
- 体脂肪の低減を促す
- 体に余分な脂肪がつきにくい
- 血中の中性脂肪の上昇をゆるやかにする など
●血圧
- 血圧が高い方に
- 血圧を抑えるのをサポートする など
●血糖値
- 血糖値が気になる方へ
- 糖の吸収をおだやかにする など
●コレステロール値
- 血中コレステロールを下げる
- 余分な体内のコレステロールを体外へ排出 など
●歯
- 歯を丈夫で健康に保つ
- むし歯の原因になりにくい など
●腸
- おなかの調子を整える
- 善玉菌を補う など
また、トクホの最大の特徴であり“信頼の証”でもある「バンザイで背伸びをしている人」のマークをパッケージに表示させることが出来ます。
機能性表示食品の場合
機能性表示食品とは、健康の維持や特定の体の働きをサポートする機能があることを、科学的根拠に基づいて表示できる食品です。パッケージにはトクホのような特徴的なマークはありませんが、必ず商品に「機能性表示食品」と明記されています。
トクホと異なる興味深い点は、必ずしもヒト試験を実施する必要がないということで、既存の研究論文や文献レビューによって、効果や機能の科学的根拠を示すことも認められています。
また、販売前に事業者が消費者庁へ届け出を行い、その内容が一般に公開されることが義務づけられており、その表示内容に対しては事業者自身が責任を負います。
他にも、それぞれの表示文言にも違いが見られます。トクホでは「〇〇の働きがあります」と明確に機能を謳うことができるのに対し、機能性表示食品では「〇〇に役立つと報告されています」と、やや控えめで間接的な表現が用いられます。つまり、機能性表示食品は「企業の責任」で科学的根拠を示し、「情報公開」が義務付けられている点が特徴であり、国による厳密な審査を経て認可されるトクホとは信頼性をどのように裏付けているかが異なります。
健康食品の臨床試験に関する質問
健康食品の効果や安全性を確かめる食品試験について、実施の目的や疑問点などをわかりやすく解説します。
Q: 健康食品を扱う臨床試験とは何ですか?
健康食品の安全性や機能性(効果)を科学的に検証するために、人を対象として行う試験のことです。消費者への信頼性向上や機能性表示食品制度への対応などで実施されています。
Q: 被験者の選定はどのように行われますか?
試験の目的に合った年齢・性別・健康状態を持つボランティアを選定します。また、インフォームド・コンセント(説明と同意)の取得が必須です。
Q: 試験の期間はどのくらいですか?
数週間から数か月が一般的ですが、効果や安全性の評価内容により変動します。
長期摂取による影響を検討する試験では1年以上のケースもあります。
Q: トクホ(特定保健用食品)として認められるにはどんな試験が必要ですか?
トクホとして認可を受けるためには、消費者庁の厳正な審査を通過する必要があり、科学的根拠に基づいたヒト試験(臨床試験)を実施することが必須となります。
なお、機能性表示食品とは異なり、トクホは「国が許可」した製品となります。
Q: 「機能性表示食品」として認められるにはどんな試験が必要ですか?
「機能性表示食品」として認められるためには、ヒトを対象とした実際の製品を使った臨床試験を実施し、臨床データや文献レビューによる科学的根拠に基づいた機能性の評価を受ける必要があります。
また、消費者庁に届け出を行い、製品の効果や内容を一般公開する義務が必要となりますが、その表示内容に対しては事業者自身が責任を負います。
まとめ
健康食品における臨床試験(治験)は、製品が人体に与える効果や安全性を科学的に証明するための重要なプロセスであり、同時に製品の信頼性やブランド価値を支える土台でもあります。
とくにトクホや機能性表示食品においては、ヒトを対象とした試験によって科学的根拠に裏付けられた高い信頼性のデータが求められます。
誰もが安心して手に取れる製品であるためにこそ、健康食品には確かなエビデンスが不可欠なのです。
著者情報

JCVN編集部
JCVNでは、病気やからだに関する様々な知識をコラムとして掲載しております。
また、ご覧いただく皆さまへ分かりやすくお伝えできるコンテンツをお届け致します。
治験とはの基礎知識一覧
- 健康食品における臨床試験(治験)とは?目的や役割を徹底解説
人気の記事
治験ボランティア登録はこちら
その他の病気の基礎知識を見る
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- PMS(月経前症候群)
- あせも
- アトピー性皮膚炎
- アルツハイマー型認知症
- アレルギー
- インフルエンザ
- ウイルス
- おたふく風邪
- がん
- クラミジア
- コレステロール
- しびれ
- とびひ
- ドライアイ
- ニキビ
- ノロウイルス
- はしか
- メタボリックシンドローム
- めまい
- リウマチ
- 不妊症
- 体重減少
- 便秘
- 前立腺肥大症
- 副鼻腔炎
- 口内炎
- 咳
- 喉の渇き
- 夏バテ
- 子宮内膜症
- 子宮外妊娠
- 子宮筋腫
- 帯状疱疹
- 心筋梗塞
- 手足口病
- 新型コロナウィルス
- 更年期障害
- 気管支喘息
- 水疱瘡
- 水虫
- 治験とは
- 熱中症
- 物忘れ
- 生活習慣病
- 疲労
- 痛風
- 糖尿病
- 耳鳴り
- 肝硬変
- 脂肪肝
- 脂質異常症(高脂血症)
- 逆流性食道炎
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)
- 関節痛
- 難聴
- 頭痛
- 頻尿
- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)
- 高中性脂肪血症
- 高尿酸血症(痛風)
- 高血圧
- 鬱病(うつ病)
こちらもよく読まれています
- 治験とは(意味やメリット・臨床試験との違い等)
- 治験の安全性 とリスク(副作用や死亡事例)
- 治験(臨床試験)参加までの流れ
- 治験モニター・ボランティアの体験談
- 病気の基礎知識
- 病気のQA
- 自己診断・健康診断
- 水虫に効く治療薬とは?おすすめの市販薬を紹介!
- 糖尿病によるめまいとは?低血糖の症状から対処法まで解説
- 逆流性食道炎の治療薬を紹介-選び方、飲む際の注意点も解説
- 糖尿病による頭痛とは?血糖値による原因から治療方法まで解説
- 骨粗鬆症(骨粗しょう症)の症状-原因や特長についても解説
- 骨粗鬆症の薬の分類と副作用を紹介!
- 頭痛薬のおすすめ5選!薬が効かないときの対応についても解説
- あせもにおすすめの薬を紹介!受診はした方が良い?予防はできる?
- 高齢者がRSウイルスに感染すると重症化する?症状や治療法、予防法について解説
- RSウイルスの対処法とは?症状から咳がひどい場合の対処法まで解説
- 便秘薬の種類・選び方を解説!おすすめ市販薬も紹介
- 口内炎におすすめの薬をトラブル別に紹介!【2024年最新版】
- 痩せる薬の種類を紹介!クリニックで処方されるダイエット薬の特徴を解説
- 治験のバイトとは?メリット・デメリットや注意点、報酬について解説