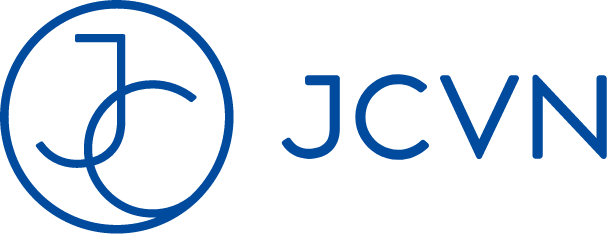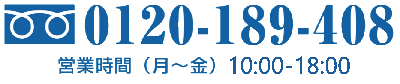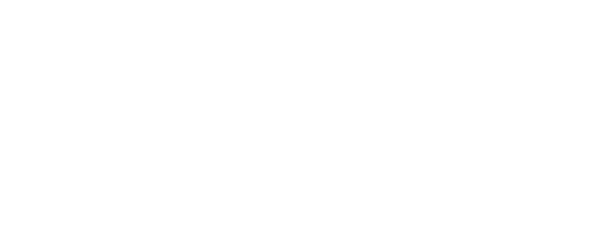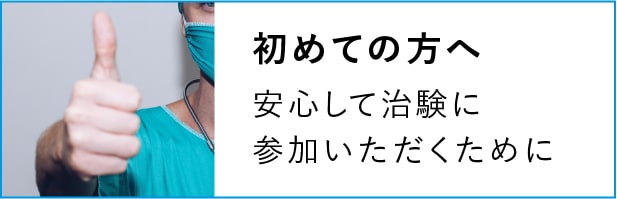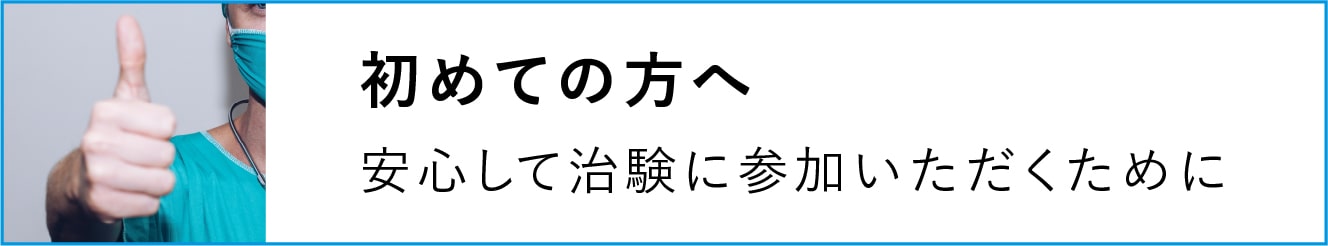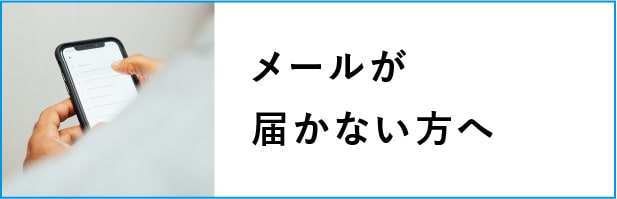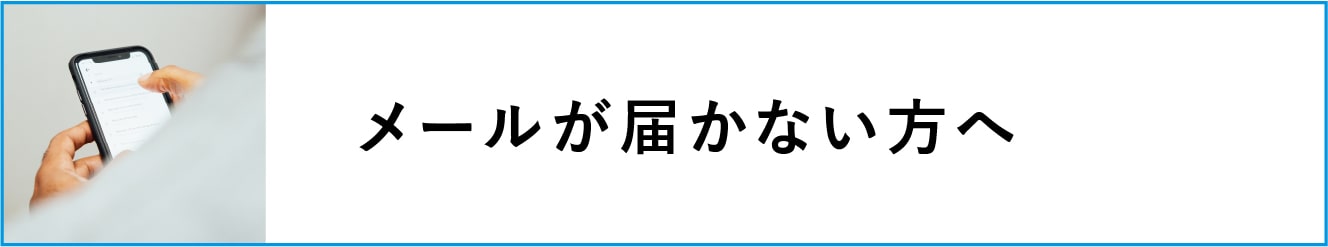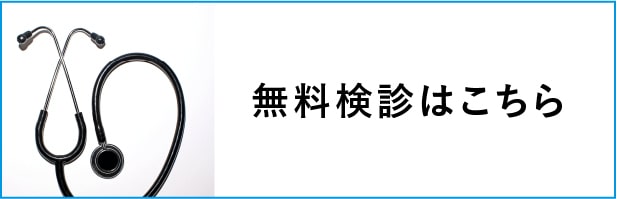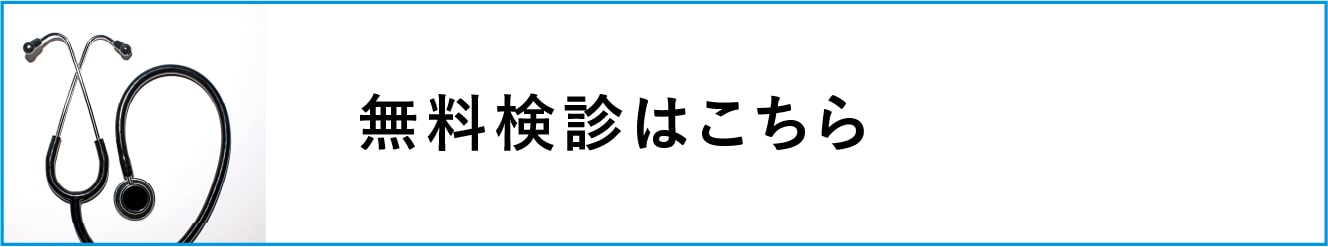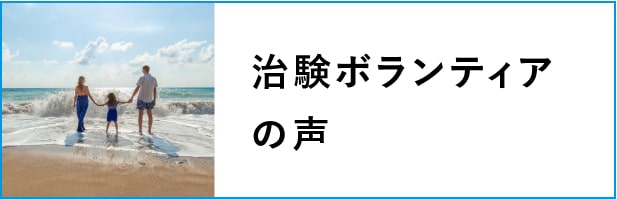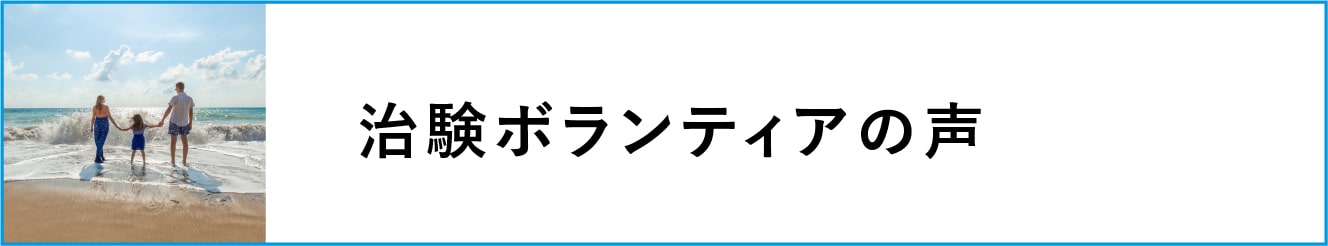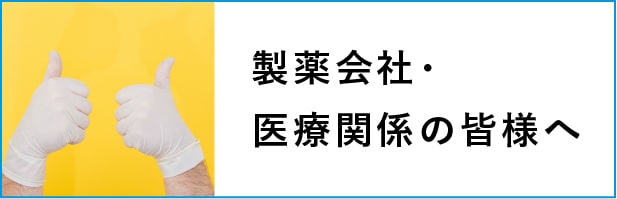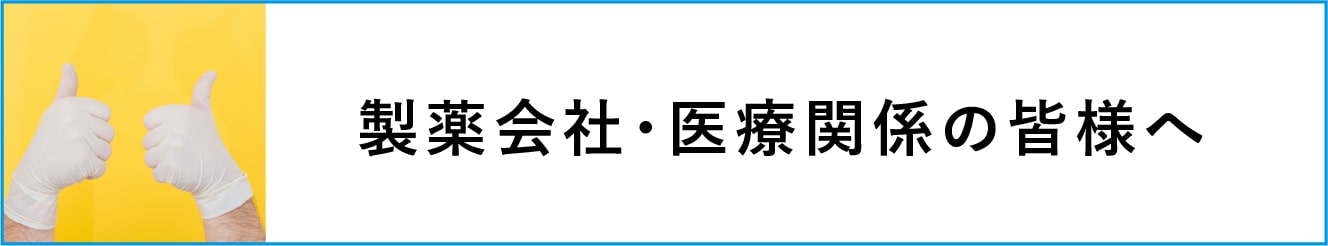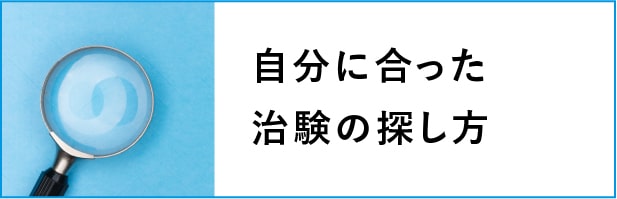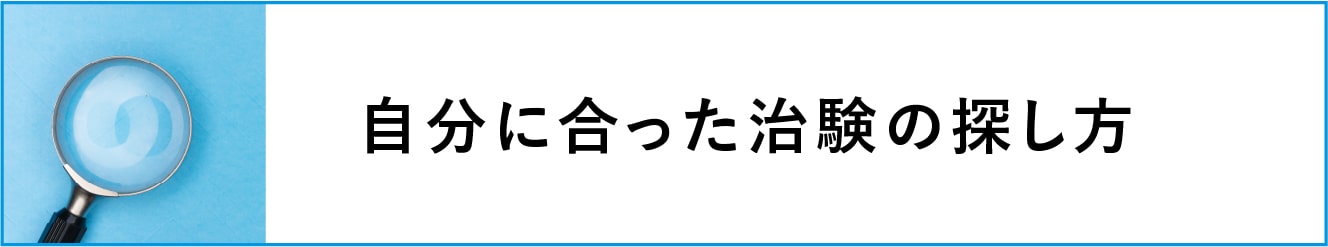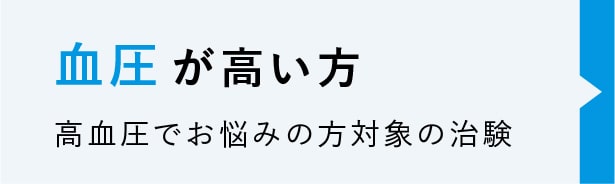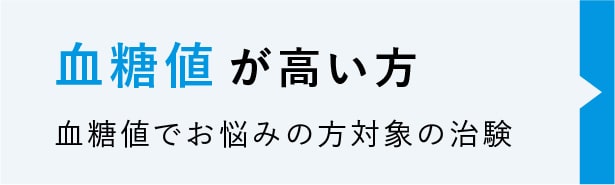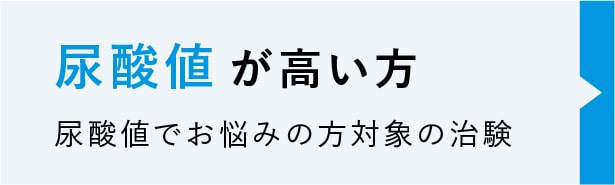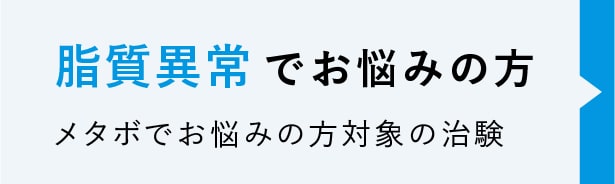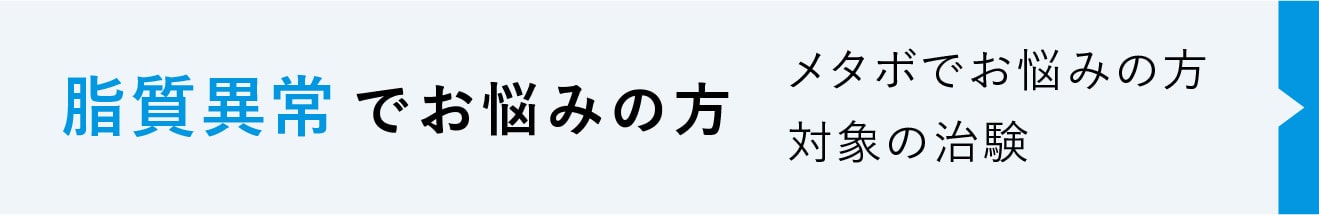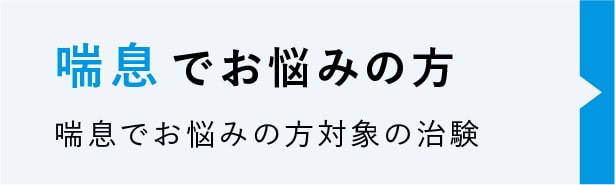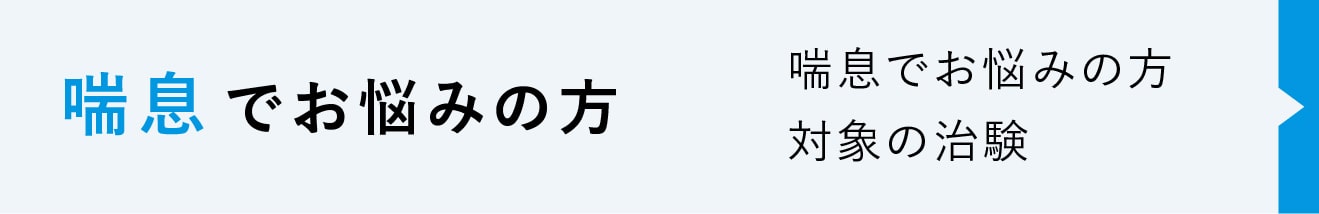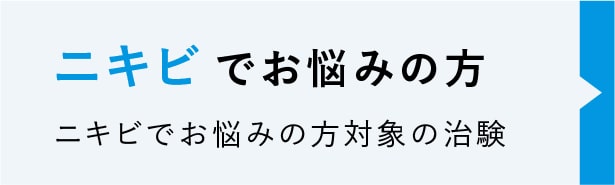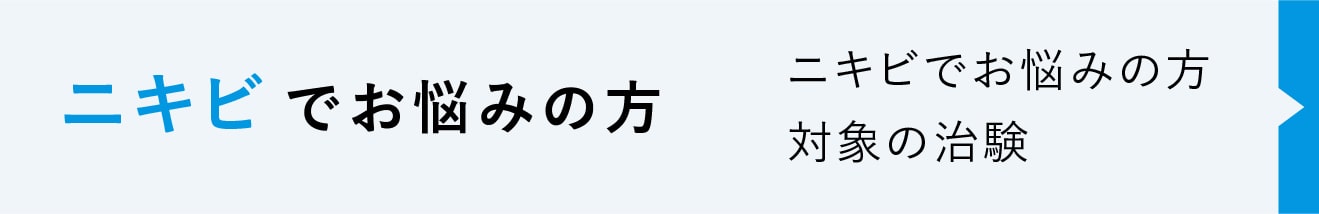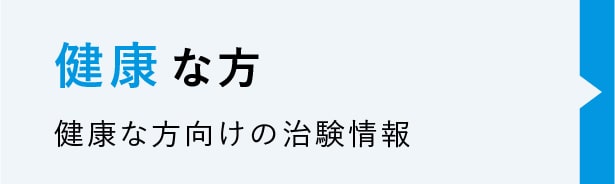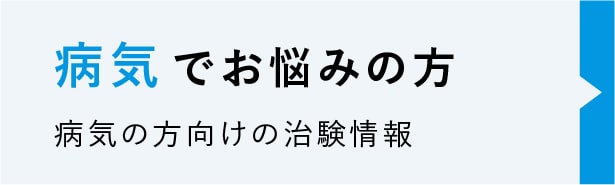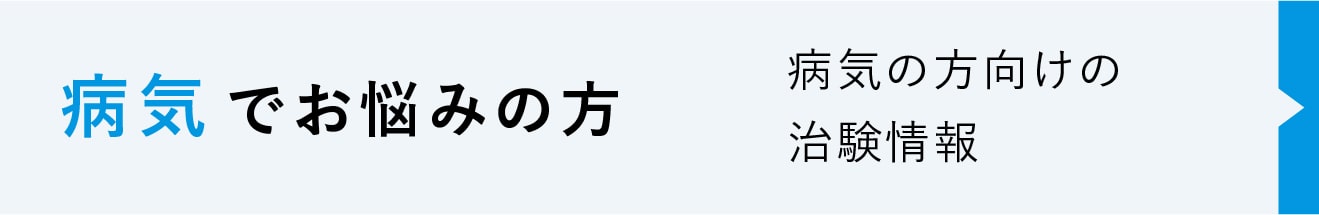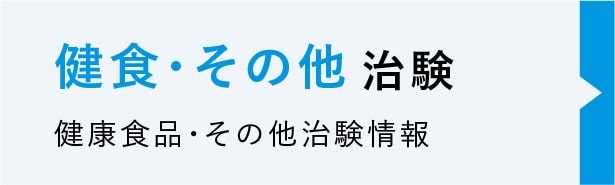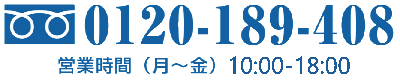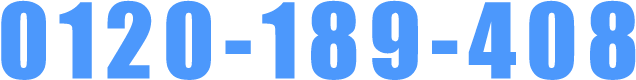【掲載日】2025/03/04
過敏性腸症候群におすすめの薬
過敏性腸症候群とは
仕事や学校で緊張した際に突然トイレに行きたくなる、外出中に突然腹痛に見舞われるなど、お腹の不調や便通異常が長期間みられる場合は過敏性腸症候群の可能性が考えられます。
過敏性腸症候群(IBS=Irritable Bowel Syndrome)とは、腸内にポリープや炎症といった構造的な異常がないにも関わらず腸の運動や機能に異常をきたし、腹痛や不快感、下痢、便秘といった症状が慢性的に続く消化器疾患です。
この症状は、腸の運動機能が過剰に反応することで下痢や便秘が繰り返される、または交互に現れるといった特徴があり、命に関わる症状ではないものの症状が慢性的に続くため、日常生活に大きな支障をきたします。
日本人成人のおよそ10~20%が罹患しているとされ、特に女性に多く見られると言われており、過敏性腸症候群は決して珍しい病気ではなく、現代では多くの人がこの症状に悩んでいます。
過敏性腸症候群の原因
過敏性腸症候群の主な原因は、過労や睡眠不足などの身体的ストレス、プレッシャーや緊張などの精神的ストレスにより、腸が過敏に反応してしまうものとされています。
これは、脳の思考や感情が腸の機能に影響し、腸の状態が脳の働きにも影響するという「脳腸相関」が関係しています。
脳と腸は自律神経やホルモンを介して密接に情報をやり取りしています。脳がストレスを感じると交感神経が活性化し、腸の蠕動運動が過剰になることで下痢を引き起こしたり、逆に低下して便秘を招いたりします。
さらに、ストレスによって腸内細菌のバランスが崩れたり、痛みを感じる神経が過敏になったりすることで、通常では気にならない腸の動きでも痛みや不快感を引き起こすことがあります。
加えて、脂っこい食事や刺激の強い食べ物を多く摂り続けると、、腸への負担が増加し症状が悪化しやすくなるので、食生活の乱れも過敏性腸症候群の発症を促す要因とされています。
このように、ストレスや生活習慣の乱れが脳と腸の相互作用に影響を与え、腸の働きや感受性を変化させることで、過敏性腸症候群の症状が引き起こされると考えられています。
過敏性腸症候群の症状
過敏性腸症候群は、腹痛や便通異常が慢性的に続く症状で、大きく3つのタイプに分けられます。
どのタイプも突然症状に見舞われることがあり、特に外出中や仕事中に急にトイレに行きたくなることで不安やストレスがさらに強くなる悪循環に陥りやすく、日常生活に大きな支障をもたらします。
下痢型
過敏性腸症候群の下痢型は、突然の強い便意や腹痛を伴う下痢が繰り返し起こるのが特徴です。特にストレスや緊張が引き金となりやすく、仕事の会議や学校の試験、通勤途中などで極度の緊張やストレスを感じた際に、急にお腹が痛くなりトイレに駆け込むケースが多くみられます。
1日に3回以上の水のような便と、トイレに行った後に症状が軽くなるといった傾向があり、いつ症状があらわれるか予測がつかないため、外出への抵抗感を抱えるなどストレスの悪循環に陥りやすい点も特徴です。
便秘型
過敏性腸症候群の便秘型は、腸の動きが鈍くなり、便が硬くなることで排便が困難になるのが特徴です。週に3回以下まで排便回数が減少し、便意を感じてもなかなか出ず、強くいきむ必要があることが多く見られます。また、排便時に腹痛が伴ったり、排便後もスッキリしない感覚やお腹の張りが続いたりなど、腹部の不快感が大きなストレスとなって過敏性腸症候群を悪化させるケースもあります。
混合型
過敏性腸症候群の混合型は、便秘型や下痢型のどちらかに特定されるのではなく、便秘と下痢の両方が交互に現れるタイプを指します。
排便が硬くて出にくい便秘の状態が続いたかと思うと、突然緩くて水様性の便になる下痢が数日間続くといったよう便通のパターンが一定しておらず、腸の働きが不安定な状態が短期間で交互に起こります。
また、腹痛やお腹の張りなどの不快感が続き、排便後に症状が軽減することが多いものの下痢と便秘のサイクルが何度も繰り返されるため、生活リズムが乱れやすく、精神的ストレスも大きくなりがちです。
過敏性腸症候群の診断・検査
過敏性腸症候群の診断には、国際的な診断基準である「ローマ基準」が採用されます。
この基準では、以下の項目に該当しているかを詳しく聞き取ります。
- 腹痛や便通異常が過去3か月間に週1回以上ある
- 少なくとも診断の6ヶ月異常前から症状が見られる
- 以下の2つ以上の項目に該当する
– 排便後に症状が緩和する
– 排便回数が変動する
– 便形状が変化する
この基準による問診に加え、血液検査、便検査、内視鏡検査を行います。
- 血液検査
炎症反応や貧血の有無を調べ、炎症性腸疾患や感染症を除外します。 - 便検査
細菌感染や血便の有無を確認します。 - 内視鏡検査(大腸カメラ)
大腸の内部を直接観察し、ポリープや潰瘍、腫瘍などの異常がないか確認します。
過敏性腸症候群の症状は、クローン病や潰瘍性大腸炎などの多くの大腸疾患と共通しているため、採血や大腸検査などが必要不可欠です。これらの検査と基準を用いて過敏性腸症候群を正確に診断し、他の疾患との鑑別を行います。
過敏性腸症候群の薬物療法
過敏性腸症候群の薬物療法は、症状に合わせた治療が基本です。下痢、便秘、腹痛といった症状ごとに適切な薬を使用し、腸の働きを整えることで症状の改善を目指します。
①抗コリン薬
抗コリン薬は、過剰な腸の収縮や痙攣を抑制することで、下痢の頻度や腹痛症状を緩和させる薬剤です。主に下痢型や混合型の症状緩和に使用されますが、過敏性腸症候群の原因を改善する効果はないため、生活習慣の改善や他の治療法と組み合わせて使用するのが一般的です。
なお、抗コリン薬は副交感神経を抑制するはたらきを持つため、口渇、便秘、頻脈、せん妄、眼圧上昇などの副作用があるため、高齢者や前立腺肥大症や緑内障を有する患者が使用する際には注意が必要です。
| 商品名 | ブスコパンA錠 20錠 |
|---|---|
| 効能・効果 | 過敏性腸症候群、胃痛、腹痛、胃酸過多、胸やけ |
| 薬のタイプ | 錠剤 |
| 用法・用量 | 1回1錠 1日3回を限度 |
②抗うつ薬
不安・緊張・抑うつ状態などが原因と見込まれる場合には、抗不安薬や抗うつ薬が有効です。これらの薬剤を低用量投与することで、腸と脳の相互作用をコントロールし、腸管の過剰な感覚を抑えて腹痛やストレスによる症状を軽減します。
ベンゾジアゼピン系と呼ばれるタイプの抗不安薬は、脳をリラックスした状態に導かせ、不安や緊張感を緩和させます。
また、うつや情緒不安定といった心理的要素が強い人へは、レクサプロやジェイゾロフトといったSSRIが使われることが多いです。
なお、飲み始めの段階では副作用として胃が気持ち悪くなったり、下痢気味になったりすることがありますが、ほとんどの場合1~2週間飲み続けると身体が慣れて自然と治まります。
| 商品名 | パキシル錠10mg |
|---|---|
| 効能・効果 | 過敏性腸症候群、強迫性障害、不安障害、うつ病 |
| 薬のタイプ | 錠剤 |
| 用法・用量 | 1回1錠 1日1回夕食後 |
| 商品名 | アモキサンカプセル25mg |
|---|---|
| 効能・効果 | 過敏性腸症候群、うつ病 |
| 薬のタイプ | 錠剤 |
| 用法・用量 | 1日25〜75mgを1〜数回に分割経口投与 |
③筋弛緩薬
筋弛緩薬は、腸管内の筋肉の緊張による以上な収縮運動を緩和し、胃腸の正常な運動を維持させることで腹痛や不快感を軽減します。まれに軽度の吐き気や下痢が生じるケースがあるものの、他の薬剤に比べて副作用が少なく、安全性が高いとされています。
主に下痢型や混合型のタイプに効果が期待されますが、こちらも原因を根治させるものではないため、症状を一時的に和らげるための補助療法として使用されます。
| 商品名 | ヂセテル |
|---|---|
| 効能・効果 | 過敏性腸症候群 |
| 薬のタイプ | 錠剤 |
| 用法・用量 | 1日1~2錠、1日3回服用 |
④グアニル酸シクラーゼC受容体作動薬
2017年に発売された新薬で、便秘型の過敏性腸症候群に対して有効とされています。
腸管の上皮細胞に存在し、消化管の機能を調整するグアニル酸シクラーゼC受容体(GC-C受容体)を活性化させることで、腸液の分泌を促進して便を柔らかくするほか、腸の運動を活発にさせることで便が移動しやすくなります。
1日1回の服用で効果を発揮するため、服薬による体へ負担が少ない利点がありますが、下痢型の過敏性腸症候群に対しては症状を悪化させる恐れがあるので注意してください。
| 商品名 | リンゼス錠0.25mg |
|---|---|
| 効能・効果 | 便秘型過敏性腸症候群、慢性便秘 |
| 薬のタイプ | 錠剤 |
| 用法・用量 | 1日1回、食前に経口投与 |
過敏性腸症候群の食事療法
過敏性腸症候群の症状は、特定の食べ物や飲み物によって悪化することがあります。症状を引き起こしやすい食品や胃腸に負担かける食材を避け、腸にやさしい食事を心がけることが食事療法の基本となります。
FODMAP食事法
FODMAPとは、発酵性オリゴ糖、二糖類、単糖類、ポリオールを代表とする小腸で消化吸収されにくく、大腸で発酵する性質を持つ糖質の総称です。これらの成分を多く含む食品は腸内で発酵しやすく、ガスや膨満感を引き起こす可能性があります。
FODMAPを多く含む食品(小麦、乳製品、果物)を制限することで、腹痛や膨満感を軽減することができます。
主な高FODMAP食品(避けるべき食品)
- 乳製品(牛乳、ヨーグルトなど)
- 柑橘類以外のフルーツ(リンゴ、ナシなど)
- 小麦やライ麦を含むパンやパスタ
- 加工食品(人工甘味料含む)
主な低FODMAP食品(推奨される食品)
- 米、グルテンフリー製品
- 柑橘類、バナナ、ベリー類
- 鶏肉、魚、大豆製品(豆腐など)
食物繊維の調整
便秘型の過敏性腸症候群の場合には水溶性食物繊維が含まれた食品が効果的です。
水に溶けてドロドロになる性質を持つ食物繊維のため、消化された食べ物が胃腸内で高い粘性を持ち、栄養素の消化や吸収を緩やかにする働きがあります。
水溶性食物繊維には、次のようなものがあります。
- ペクチン:りんご、プルーン、野菜などに含まれる
- アルギン酸:昆布、わかめ、ひじきなどの海藻類に含まれる
- グルコマンナン:こんにゃく、山芋、里芋などに含まれる
- ガム質:大麦、オーツ麦、グアー豆などに含まれる
- イヌリン:菊芋、チコリ、にんにく、玉ねぎなどに含まれる
腸内環境を整える食品
乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを含む食品は、腸内の善玉菌を増やし、症状を緩和するのに役立つとされています。
プロバイオティクスは、ヨーグルトや納豆、ぬかづけなどの発酵食品に多く含まれ、昨今ではサプリメントや美容製品に含まれている商品なども販売されています。
刺激物の制限や食事方法
高脂肪食品やアルコール、カフェイン、辛い食べ物などは腸を刺激し、症状を悪化させることがあります。また、急いで食べることや食べ物と一緒に大量の水を同時に摂ることも症状を悪化させる可能性があります。
まとめ
過敏性腸症候群の治療には、症状がどのタイプに該当するかを把握し、症状に応じた薬を選択することが重要です。一方で、薬物療法は症状緩和を目的とし、過敏性腸症候群の原因を解消させる効果を有していません。
普段の生活の改善や簡単に自宅で取り入れられる食事療法と併用することで、より効果的な治療が期待できます。
過敏性腸症候群(IBS)の基礎知識一覧
- 過敏性腸症候群のセルフチェック-症状・原因・治療方法について解説
- 過敏性腸症候群におすすめの薬
人気の記事
治験ボランティア登録はこちら
その他の病気の基礎知識を見る
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- PMS(月経前症候群)
- あせも
- アトピー性皮膚炎
- アルツハイマー型認知症
- アレルギー
- インフルエンザ
- ウイルス
- おたふく風邪
- がん
- クラミジア
- コレステロール
- しびれ
- とびひ
- ドライアイ
- ニキビ
- ノロウイルス
- はしか
- メタボリックシンドローム
- めまい
- リウマチ
- 不妊症
- 体重減少
- 便秘
- 前立腺肥大症
- 副鼻腔炎
- 口内炎
- 咳
- 喉の渇き
- 夏バテ
- 子宮内膜症
- 子宮外妊娠
- 子宮筋腫
- 心筋梗塞
- 手足口病
- 新型コロナウィルス
- 更年期障害
- 気管支喘息
- 水疱瘡
- 水虫
- 熱中症
- 物忘れ
- 生活習慣病
- 疲労
- 痛風
- 糖尿病
- 耳鳴り
- 肝硬変
- 脂肪肝
- 脂質異常症(高脂血症)
- 逆流性食道炎
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)
- 関節痛
- 難聴
- 頭痛
- 頻尿
- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)
- 高中性脂肪血症
- 高尿酸血症(痛風)
- 高血圧
- 鬱病(うつ病)