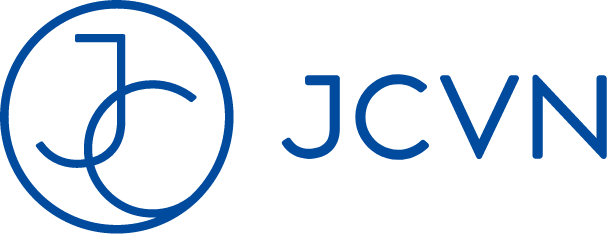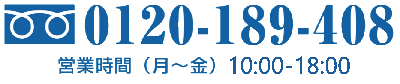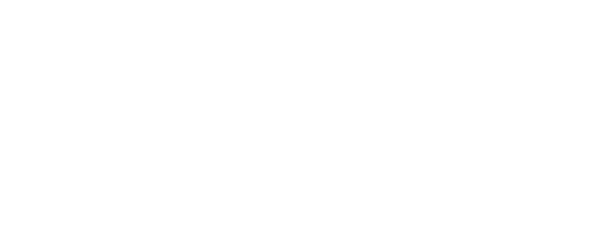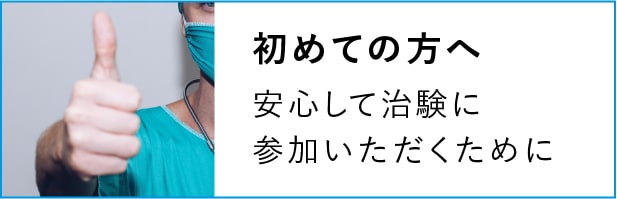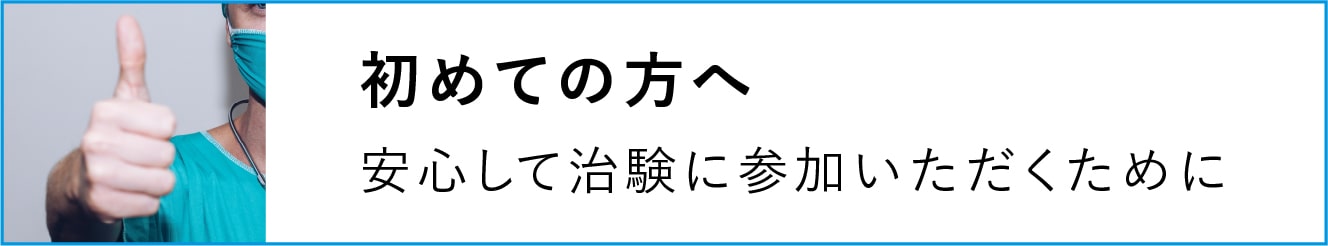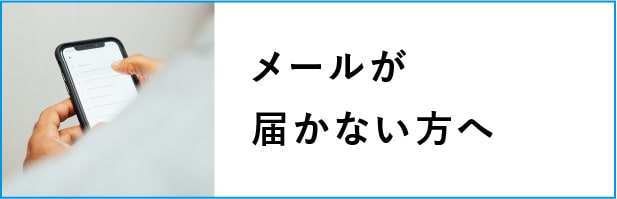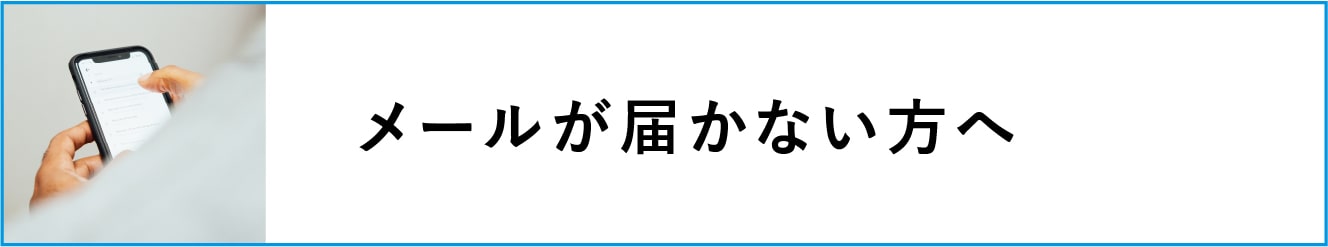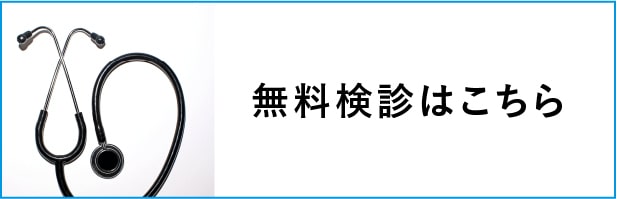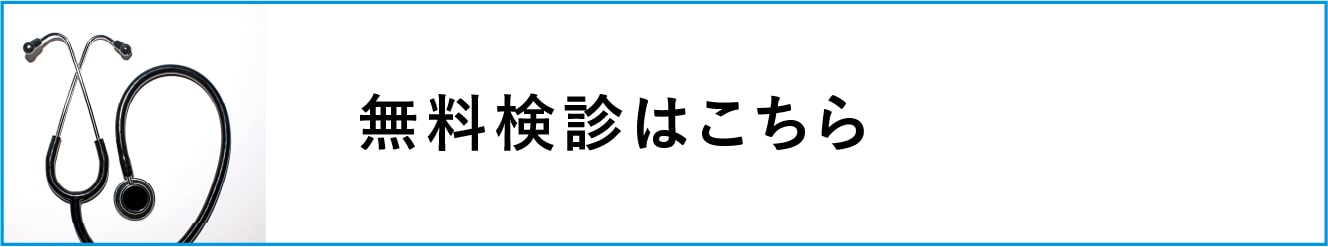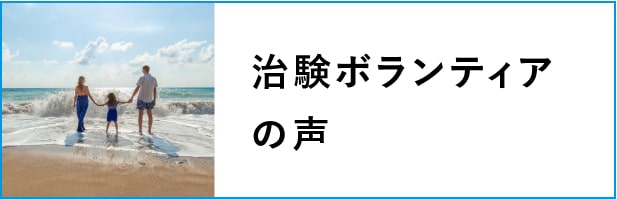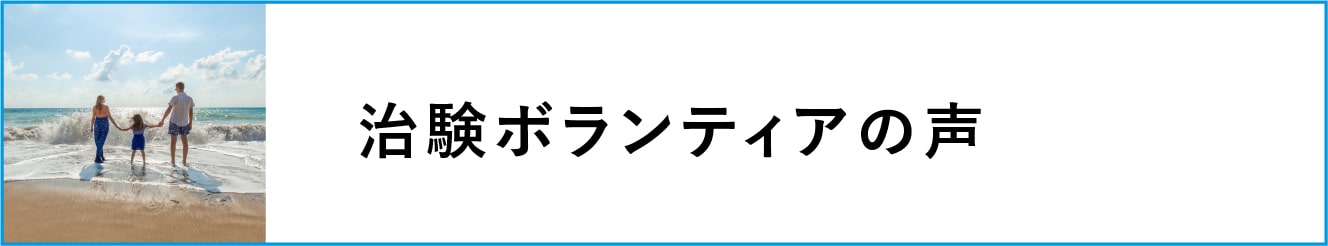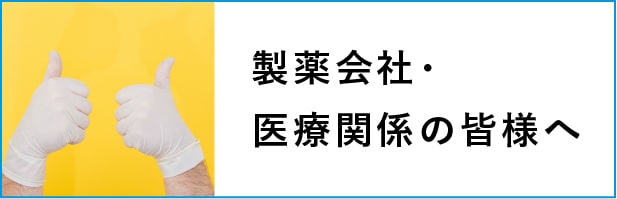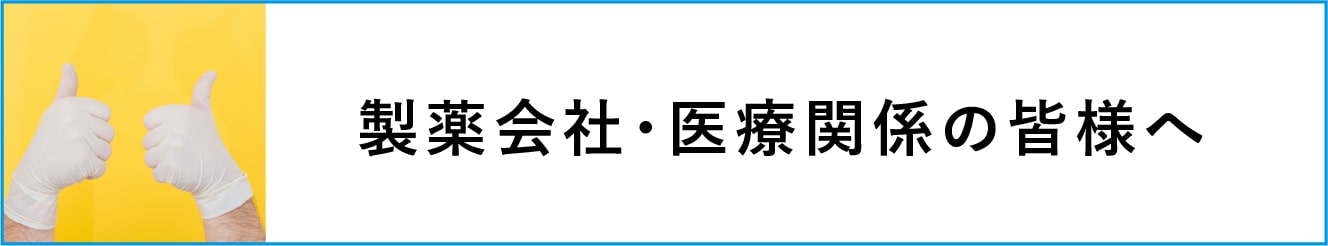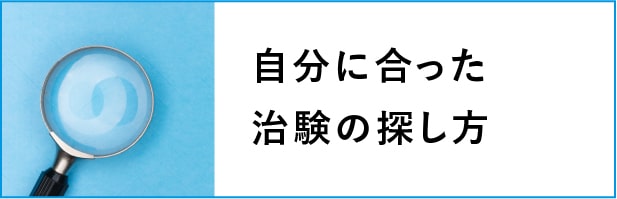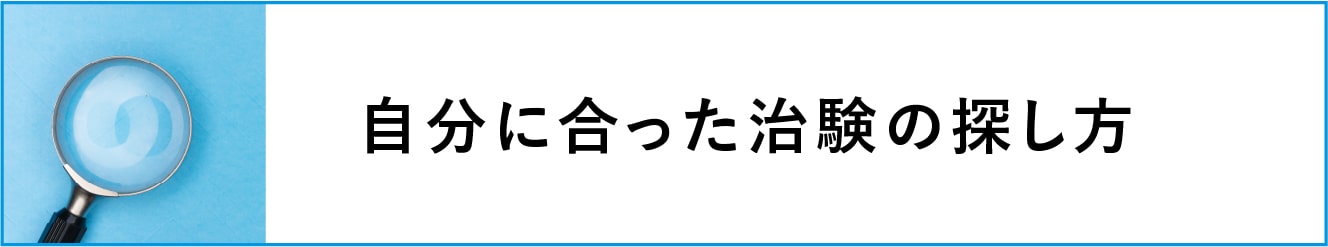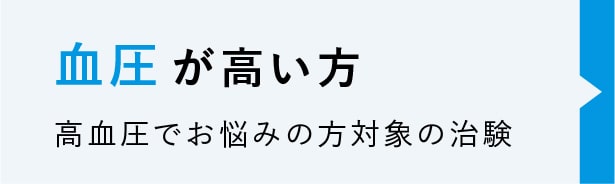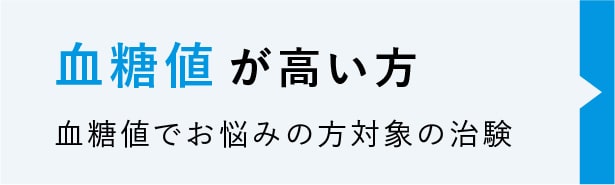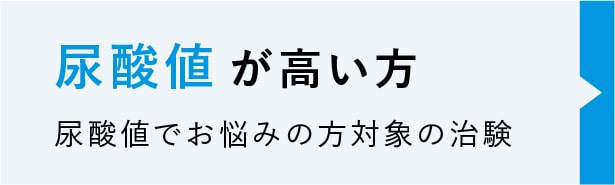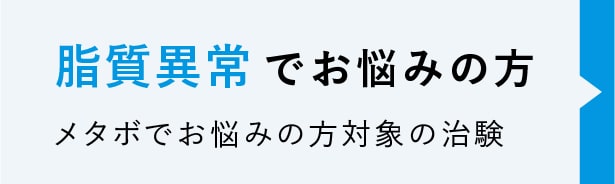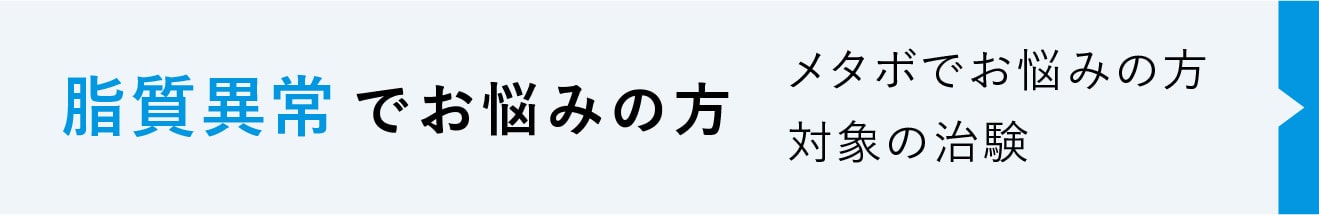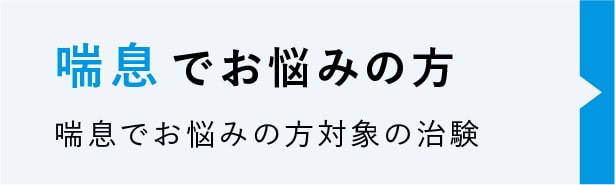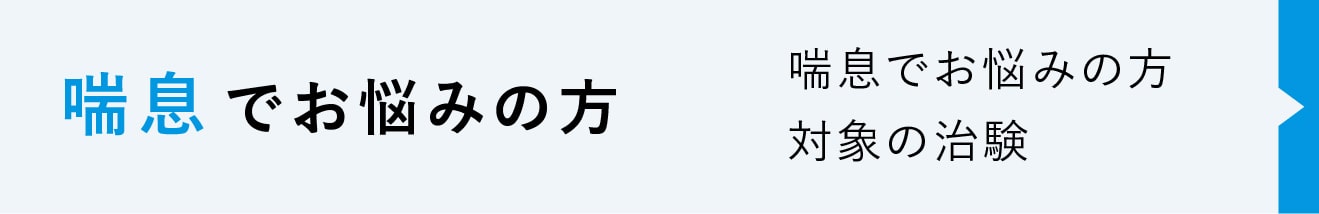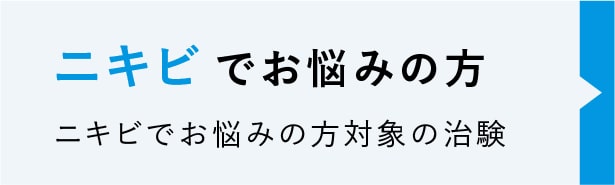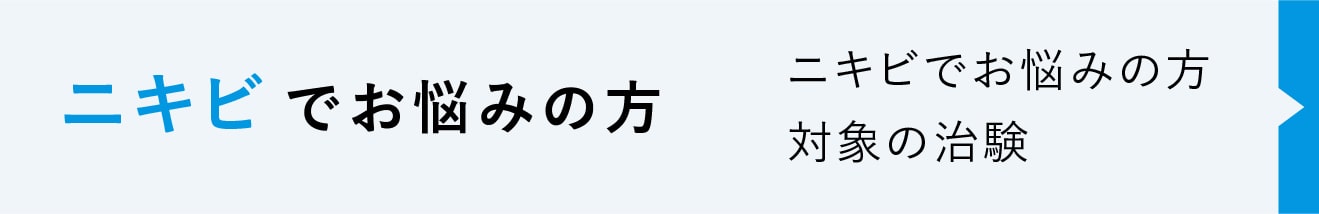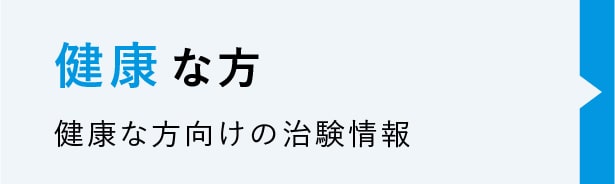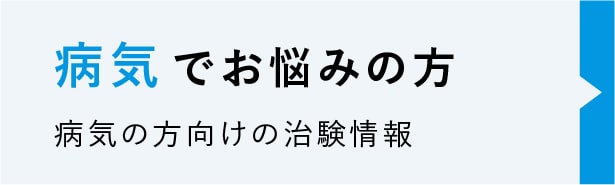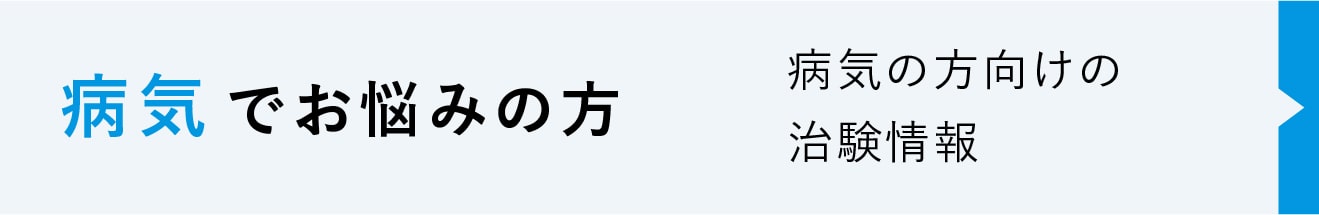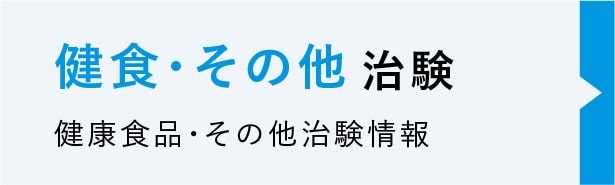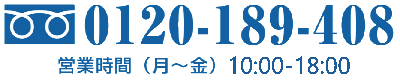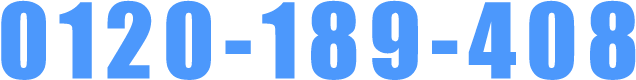【掲載日】2021/05/25 【最終更新日】2023/06/21
熱中症の症状とは?原因や治療・予防法を徹底解説

-
監修者
内科医・公衆衛生医師
成田亜希子医師
熱中症の症状とは?
熱中症は、高温多湿な環境下において、体温が上昇することでさまざまな症状を引き起こす病気です。暑さによって大量の汗をかくことで体内の水分と電解質が失われることが根本的な原因です。
熱中症の主な症状は以下の通りとなります。
- めまいや顔のほてり
- 立ちくらみ
- 筋肉痛や筋肉のけいれん
- 体のだるさや吐き気
- 汗のかきかたがおかしい(大量に汗をかく、汗がほとんど出ないなど)
- 頭痛
- 体温が高い
- 呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない
熱中症の症状と重症度
◆軽度な熱中症
- めまい・失神
→「立ちくらみ」という状態で、脳への血流が瞬間的に不充分になったことを示します - 筋肉痛・筋肉の硬直
→筋肉の「こむら返り」のことで、その部分の痛みを伴います。発汗に伴う電解質の欠乏により生じます - 大量の発汗
◆中度な熱中症
- 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感
→体がぐったりする、力が入らないなど
◆重度な熱中症
- 意識障害・けいれん・手足の運動障害
→呼びかけや刺激への異常反応、体のひきつけ、真直ぐ走れない・歩けないなど - 高体温
→体に触れると熱い状態
最初は体温が上がらないこともある
熱中症になっても、軽症のうちは体温が高くならないこともあります。ただし、最初は軽症でも、放置することで重症化することもあります。野外など暑い場所や湿度が高い場所で活動をしているときに体の異常を感じることがあったら涼しいところで安静にして症状が落ち着くまでゆっくり休みましょう。ただし、中等度以上の症状がある場合は失われた水分を補給するために点滴治療などが必要になることも少なくありません。できるだけ早めに医療機関を受診しましょう。
熱中症の3大要因
熱中症が起こる原因は、外気温が高いことで体にたまった熱を体外に逃がすことができなくなり、体温が体内に蓄積することによって起こります。そして、熱中症が起こる原因には環境、身体、行動の3つが関係しているとされています。
環境
外気の温度や湿度が高くなったりすると身体から熱が逃げていかなくなります。そのため炎天下の屋外、体育館、工事現場、気密性の高い建物や、窓を閉め切った日差しの強い部屋においては熱中症になる可能性が高くなります。
身体
身体的な特徴として、汗をかきにくい高齢者、体温がもともと高く体にたまりやすい乳幼児は熱中症にかかるリスクが高いです。
特に乳幼児は身長が低かったりベビーカーに乗っていたりと地面に近いため輻射熱といい、地面から放射された熱が伝わってしまい熱中症となるリスクが高まります。
また、低栄養や下痢、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかっている方、多量の飲酒をする方や二日酔いの方は、水分が不足しやすいため熱中症になりやすいと言えます。
行動
長時間の屋外での作業や十分な水分補給を行わない状態での運動などです。
熱中症を予防するためには上記要因を回避することが対策につながります。
熱中症の治療法とは?
軽度の場合は、重症化を防ぐためにまずは体を冷やして熱を下げ、水分と塩分を補給するとことが大切です。体温を下げるための冷却措置としては、直射日光を避けて、クーラーや扇風機などがある涼しい場所へと移動し、体温を下げるために、首や脇の下、足のつけ根に水をかけたり氷を当てたりして冷やすほか、衣服の締め付けをゆるめるなどの対策が有効です。
水分補給を行う際は、塩分を含まない水分だけでは電解質の不足が補えないため、電解質を含む経口補水液やスポーツ飲料が望ましいと考えられます。
重度の場合は速やかに救急車を呼び、到着までの間に冷却処置や水分補給を行いましょう。必要に応じて水分や電解質を補充するための点滴などが行われます。
熱中症の予防策とは?
高温多湿の環境下での活動を回避し、水分はこまめに摂取することを心がけましょう。
また、暑い季節は体に熱がこもらないように通気性の良い素材の服を着用しましょう。
万が一、体の不調を感じた場合は速やかに涼しい場所へ移動し、水分を補給して安静にしてください。
熱中症の基礎知識一覧
- 熱中症の症状とは?原因や治療・予防法を徹底解説
人気の記事
治験ボランティア登録はこちら
その他の病気の基礎知識を見る
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- PMS(月経前症候群)
- あせも
- アトピー性皮膚炎
- アルツハイマー型認知症
- アレルギー
- インフルエンザ
- ウイルス
- おたふく風邪
- がん
- クラミジア
- コレステロール
- しびれ
- とびひ
- ドライアイ
- ニキビ
- ノロウイルス
- はしか
- メタボリックシンドローム
- めまい
- リウマチ
- 不妊症
- 体重減少
- 便秘
- 前立腺肥大症
- 副鼻腔炎
- 口内炎
- 咳
- 喉の渇き
- 夏バテ
- 子宮内膜症
- 子宮外妊娠
- 子宮筋腫
- 心筋梗塞
- 手足口病
- 新型コロナウィルス
- 更年期障害
- 気管支喘息
- 水疱瘡
- 水虫
- 熱中症
- 物忘れ
- 生活習慣病
- 疲労
- 痛風
- 糖尿病
- 耳鳴り
- 肝硬変
- 脂肪肝
- 脂質異常症(高脂血症)
- 逆流性食道炎
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)
- 関節痛
- 難聴
- 頭痛
- 頻尿
- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)
- 高中性脂肪血症
- 高尿酸血症(痛風)
- 高血圧
- 鬱病(うつ病)