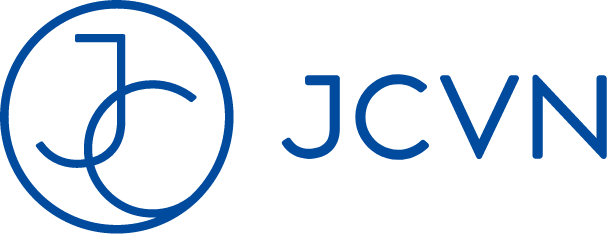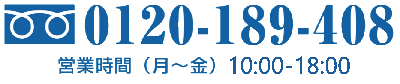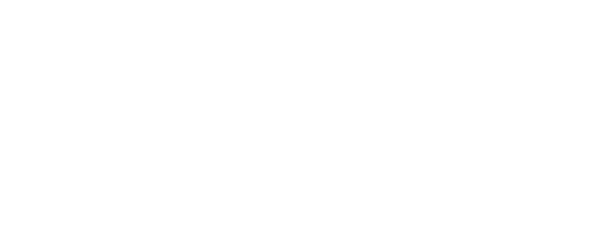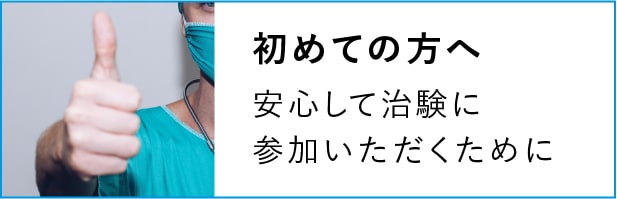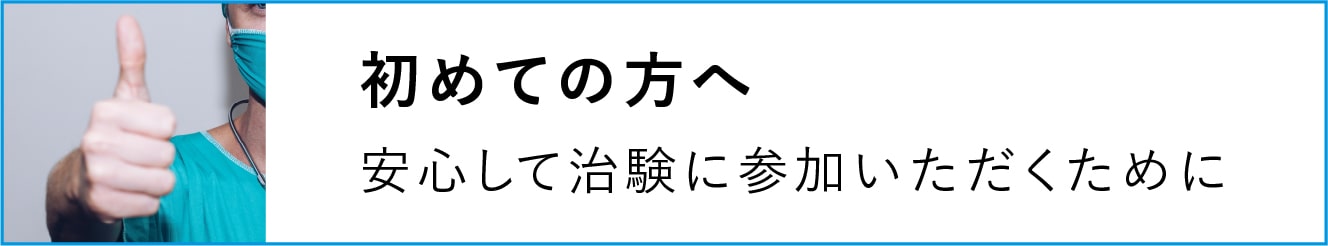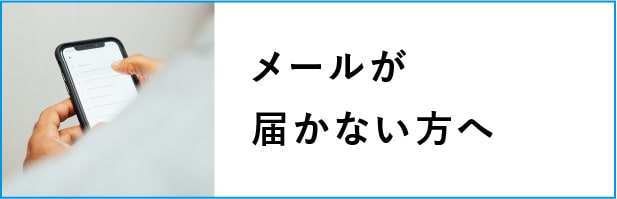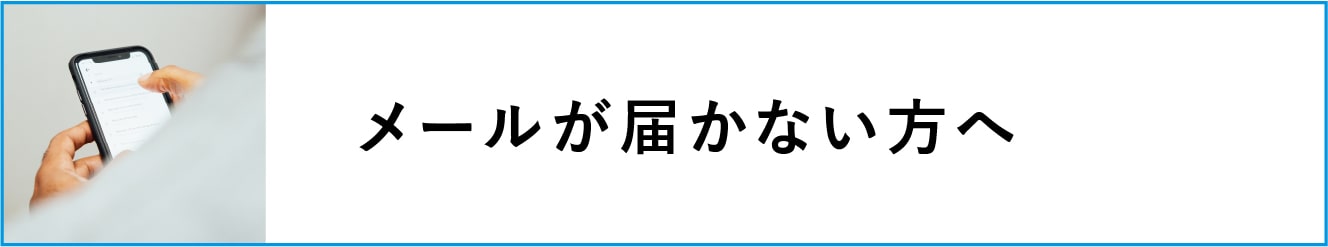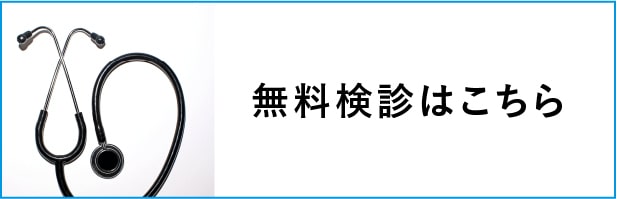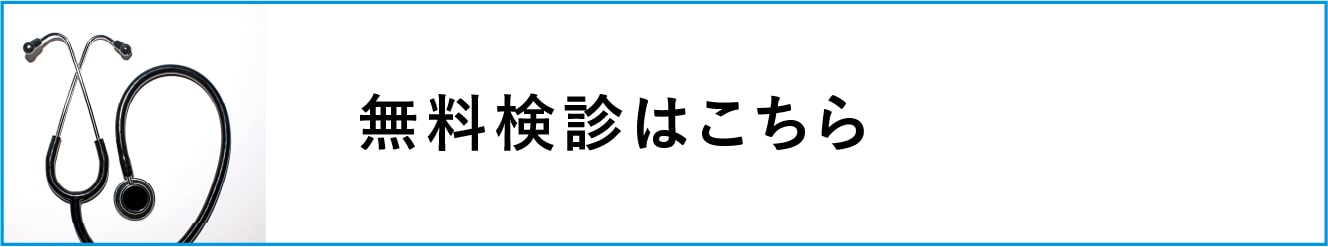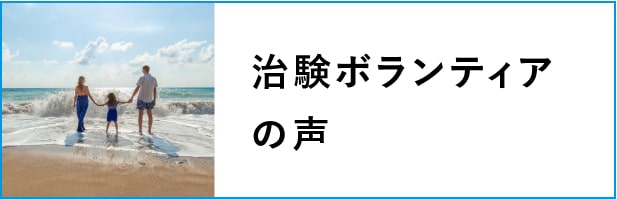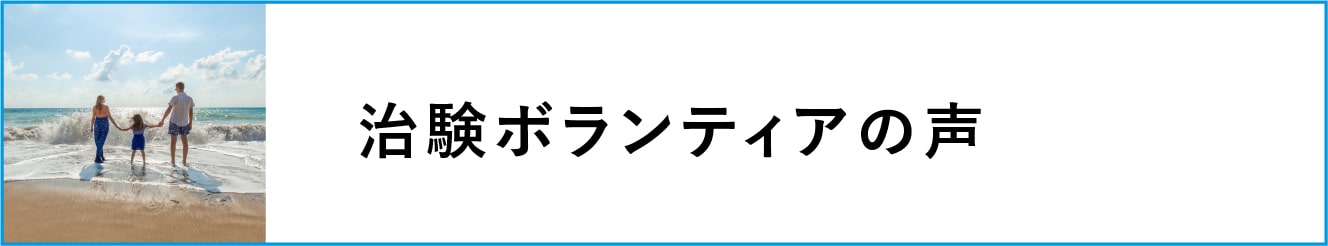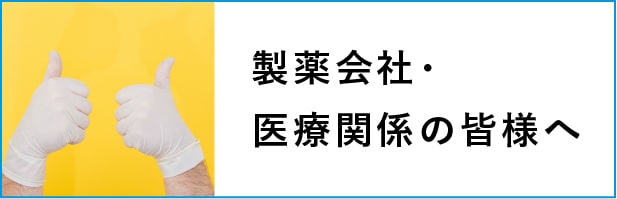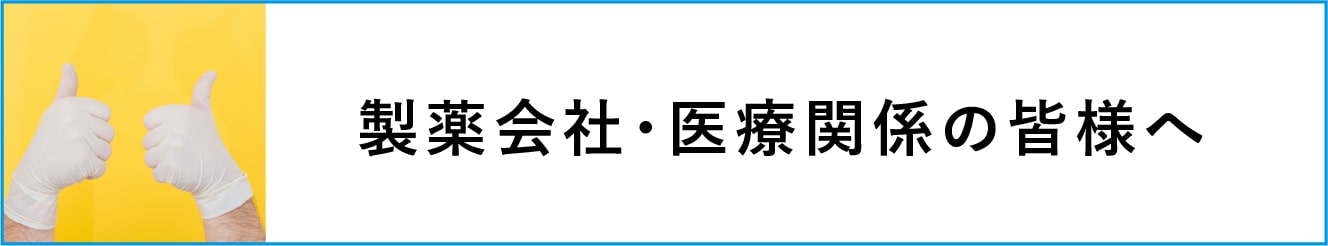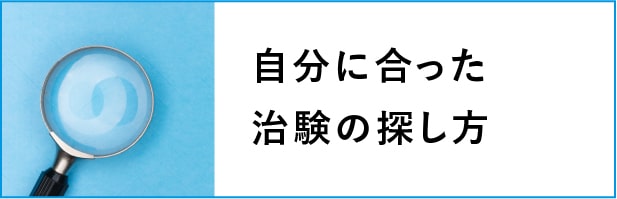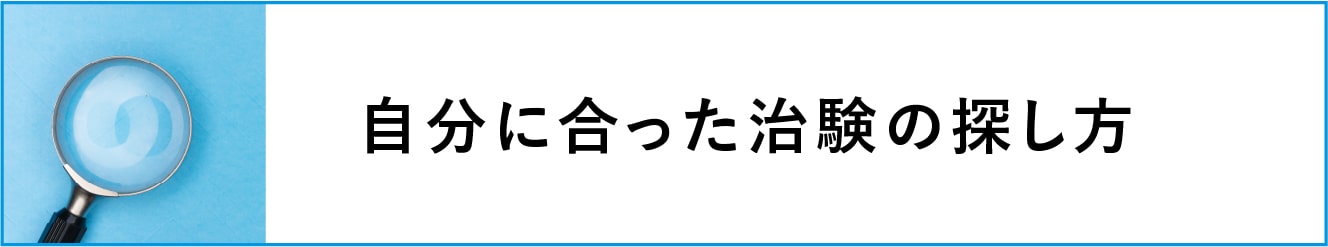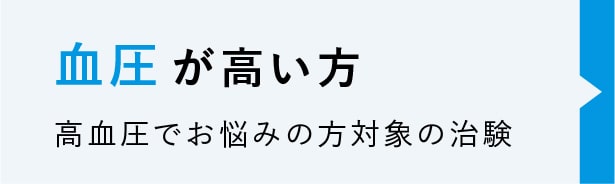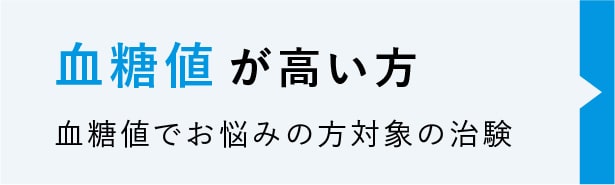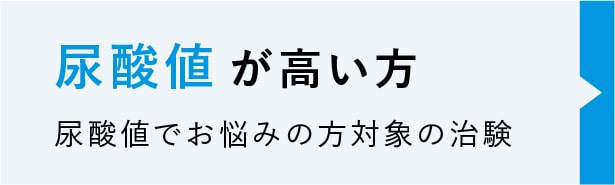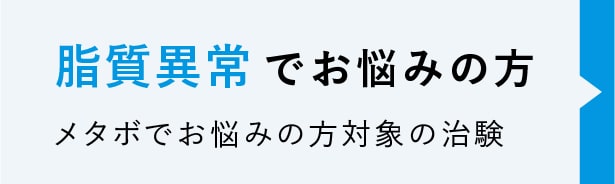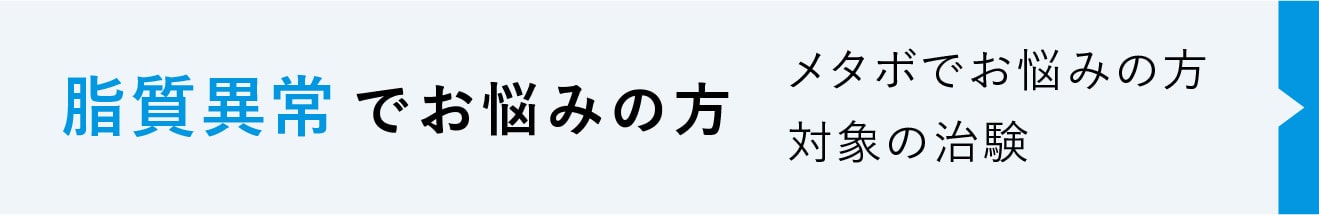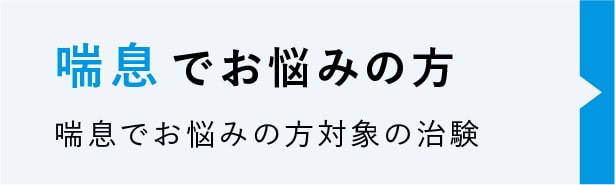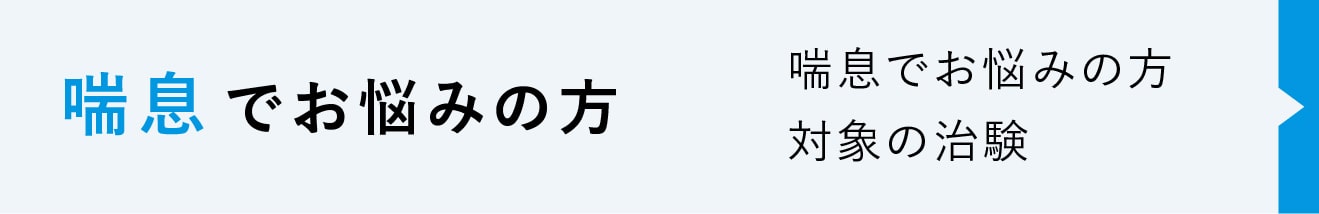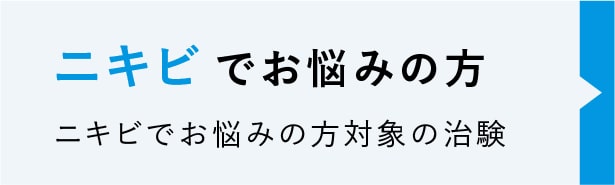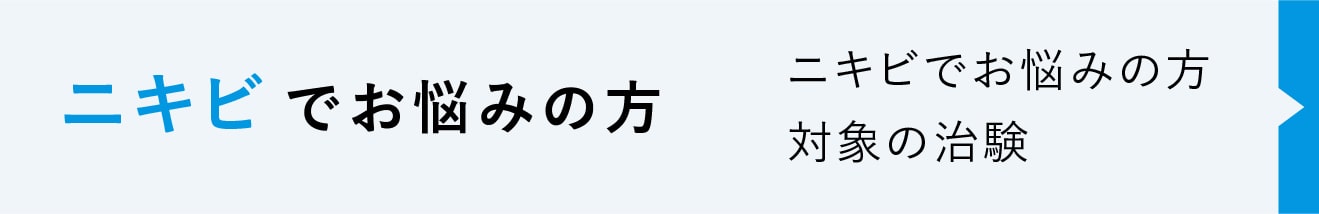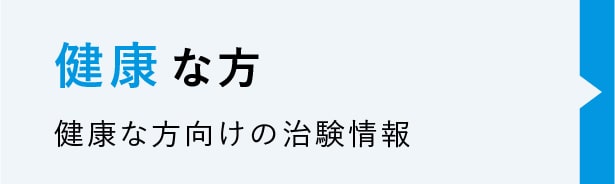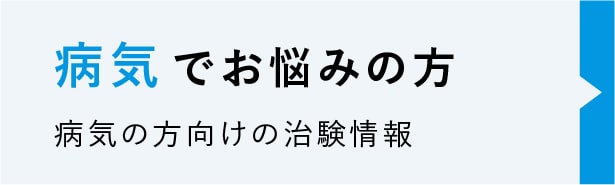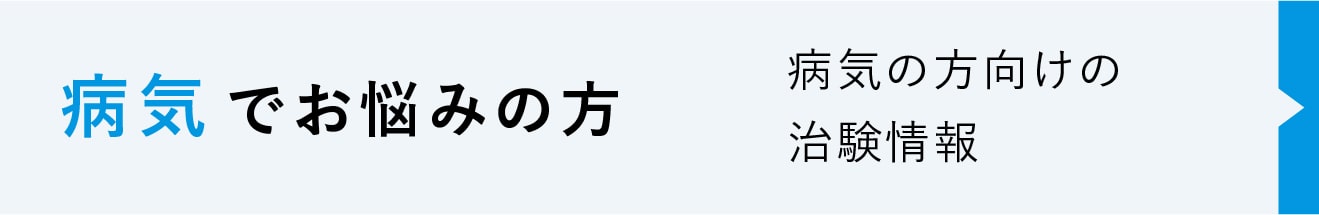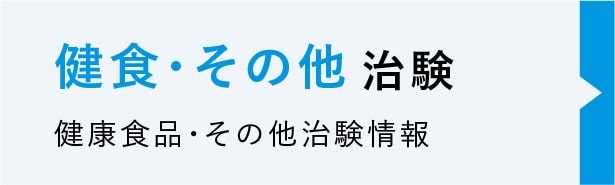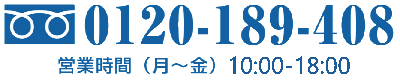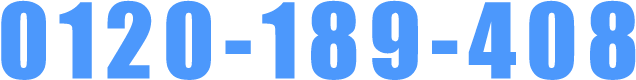【掲載日】2025/05/22
脂肪肝を改善する方法はある?原因から食事のポイントまで徹底解説
当コラムの掲載記事に関するご注意点
1. 本コラムに掲載されている情報は、記事により薬剤師や医師など医療・健康管理に関する専門資格を有する方による執筆または一部監修を入れ評価検証を行った上で掲載しております。掲載内容については掲載時点での情報をもとに可能な限り正確を期すよう、当社自身でも慎重に確認を行っておりますが、記事によっては執筆者本人の見解を含むものもあり、正確性や最新性あるいは具体的な成果を保証するものではありません。あくまでも読者の皆さまご自身の判断と責任において参考としてご利用ください。また、掲載後の状況変化等により予告なく記事の修正・更新・削除を行う場合があります。
2. 本コラムにおける一般用医薬品に関する情報は、読者や消費者の皆さまが適切な商品選択を行えるよう支援することを目的に作成しているものです。また、当該コラムの主な眼目は「商品」ではなく「成分」にあり、特定商品の広告目的や誘引を企図したものではありません。併せて、特定の医薬品メーカーや販売業者から紹介や販売を目的とした報酬などの対価を受け取っているものでもありません。
3. 本コラムに記載されている商品名やサービス名は、それぞれの提供元または権利者に帰属する商標または登録商標です。
4. 前述の内容に関連して、読者の皆さまに万一何らかの不利益や損害が発生した場合でも、当社はその一切について責任を負いかねます。
5. 本コラムに関する個別のお問合せには一切応じておりませんが事実と異なる誤った記載があった場合はご指摘のご連絡を頂けますと幸いです。
脂肪肝とは?
脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が過剰に蓄積する病気です。
通常、食事で摂取した糖質や脂質は脂肪酸やブドウ糖に分解され、小腸から吸収された後、エネルギー源として肝臓に蓄えられます。しかし、食べ過ぎや運動不足などの生活習慣の乱れにより、消費しきれなかったエネルギーが肝臓に中性脂肪として残ってしまうと、脂肪肝を引き起こします。
脂肪肝そのものに痛みなどの自覚症状はありませんが、肝臓の全体の30%以上が脂肪で占められている場合が多く、肝機能の低下とともに次第に血流が悪化し、全身の細胞に酸素や栄養分が行き渡らなくなることで、疲労感や肩こり、肝機能数値の異常などの前兆が現れることがあります。
また、脂肪肝の多くはメタボリックシンドロームを合併しており、放置すると肝機能の悪化や肝炎・肝硬変へと進行する可能性があります。さらに、脂質異常症(高中性脂肪)や糖尿病を誘発し、動脈硬化を進行させるリスクも高まります。
厚生労働省の調査によると、日本人男性の約40%が脂肪肝と診断されているとの調査結果もあり、特に日本人では見た目が痩せ型でも脂肪肝と診断されるケースがあり、肥満でなくても肝臓に脂肪が蓄積する可能性があります。
脂肪肝の原因は?
インスリン作用の低下
エネルギーを体内で生成するには、インスリンと呼ばれるホルモンの働きが必要です。
つまり、インスリンの機能が低下したりインスリンそのものが分泌されなかったりすると、体内で十分なエネルギーを生成することができずに肝臓に脂肪が溜まりやすい環境をつくってしまいます。
肥満によって内臓脂肪が増えると、脂肪細胞の肥大化や遊離脂肪酸の増加、運動により筋肉がブドウ糖を消費しないなどでインスリンが臓器に作用しづらくなる状態(インスリン抵抗性)を引き起こしてしまいます。また、血糖値が高い人や糖尿病と診断されている人も体内でインスリンを生成しづらい状態になっているため、中性脂肪が体内に留まりやすくなってしまいます。
アルコールの過剰摂取
肝臓には、アルコールや有害物質を分解・解毒する重要な働きがあります。アルコールが体内に入ると、肝臓で最終的に酢酸へと代謝されます。この過程で生成される物質(NADH)は、脂肪酸の分解を抑制する働きがあるため、アルコールを過剰に摂取すると肝臓に脂肪が蓄積し、アルコール性脂肪肝を引き起こしやすくなります。
運動不足や無理なダイエット
運動不足により消費エネルギーが低下すると、余分な糖や脂質が中性脂肪として肝臓に蓄積されやすくなるとともに筋肉量が減ることでインスリン抵抗性が高まり、脂肪の代謝が悪化することも脂肪肝の進行を助長します。
一方、極端なダイエットで急激に体重を落とすと、脂肪が一気に分解されて肝臓に流れ込み、低栄養性脂肪肝を引き起こすことがあります。
脂質異常症と高脂血症との違いとは?放置するリスクや治療中の注意点を解説
脂肪肝にはどんな症状がある?
初期症状
肝臓機能の低下によりエネルギー代謝が悪化し、慢性的な疲労感や倦怠感を感じやすくなります。また、全身の血流が悪くなり酸素や栄養の供給が滞ることで、体が重く感じたり肩こりや頭痛がみられたりするようになります。しかし、これらの症状は一時的な体調不良や他の病気と関連して発症することも多いため、初期症状だけで脂肪肝が原因と断定することは難しいです。
初期症状とともに健康診断の血液検査で肝機能系の数値(AST・ALT・γ-GTP)が上昇している場合は、脂肪肝のリスクがあると判断しましょう。
進行後症状
脂肪肝の状態が続くと肝細胞がダメージを負い、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)やアルコール性肝炎などの炎症が発生します。これらの肝炎が進行すると肝臓の組織が傷つき黄疸や腹部の膨満感などが現れることがあります。
さらに悪化すると肝臓に線維化が生じ、肝硬変へと進行します。肝硬変になってしまうと肝臓は十分に機能しなくなり肝不全や肝臓がんなど、死亡リスクの高い病気へと進行します。
脂肪肝の改善方法は?
有酸素運動
脂肪肝の症状だけでなく、運動は体内に蓄積した脂肪を減少させる重要な手段です。
特に、ジョギング・サイクリング・水泳をはじめとする有酸素運動は、1回30分以上、週3~5回行うことで脂肪の燃焼が促進されます。また、適度な運動はインスリンの感受性を高め、脂肪の蓄積を抑える効果もあります。有酸素運動の習慣を継続することで、肝臓にたまった中性脂肪を減らしながら脂肪肝の進行を防ぎことが期待できます。
筋力トレーニング
スクワット・腹筋・腕立て伏せなどの筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、基礎代謝を向上させる効果があります。基礎代謝が高まることで体が消費するエネルギー量が増え、脂肪が燃えやすい体質へと変化します。
筋力トレーニングと先述の有酸素運動を組み合わせるだけで、脂肪の分解と消費を効率的に促進することができます。
中性脂肪の元となる糖質と脂質の摂取を適正化する
中性脂肪の量が体内で増加しないために、普段の食事に含まれている糖質や脂質の摂取量に気をつけることも脂肪肝を改善するポイントです。
過剰な糖質や脂質の摂取は中性脂肪に変換されやすいため、精製された炭水化物(白米・パン・麺類・砂糖)や飽和脂肪酸(揚げ物・バター・加工食品)を控えましょう。
食物繊維の多い野菜や玄米、雑穀、EPAやDHAを含む魚の脂やオリーブオイルなどの不飽和脂肪酸を代替すると、脂肪の蓄積を抑制し、代謝を促進しやすくなります。
また、肥満体型の方は体重の5%を減らせば脂肪肝の約30%は改善できるとも言われているので、目安を掲げた無理のないダイエットも効果的です。
例)体重80kgの場合、80kg×5%=4kgの減量が目安
脂肪肝を改善するための食事のポイントは?
糖質を抑える
脂肪肝を改善するうえで最も注意すべきなのは、炭水化物の過剰摂取です。体が必要とする以上の糖質を摂取すると、エネルギーとして使われなかった分が余剰となり、脂質へと変換され体内に蓄積されてしまいます。
一般的な日本人の食生活では一日の総エネルギーの約60%を糖質が占めていますが、これを約50%に抑えることで、無理なく摂取量をコントロールできます。
体格によって適量は異なりますが、まずは主食である炭水化物(白米・パン・麺類)の量を1割程度減らすことを目安とすると良いでしょう。
また、食物繊維の多い野菜や玄米、雑穀を代わりに摂取すると、食後の血糖値の上昇を緩やかにし、脂質の吸収を抑える効果があります。
糖分を抑える
糖分の過剰摂取は、肥満や血糖値上昇によるインスリン作用の低下を促進するため、エネルギーとして活用されなかった糖分は中性脂肪として残りやすくなってしまいます。
特に、清涼飲料水・スポーツドリンク・フルーツジュースなどには大量の砂糖が含まれており、1杯だけでも多くの糖分を摂取してしまいます。また、甘い飲み物を飲むと血糖値が上昇し、それを薄めようとして水が欲しくなるため、のどの渇きを感じ、さらに甘い飲料を飲んでしまう悪循環に陥ってしまいます。
飲み物は糖分が含まれるジュース類ではなく水や無糖の茶類を選ぶように気をつけましょう。
脂肪肝が進行するとどんな病気になる恐れがある?
アルコール性脂肪性肝炎(ASH)
アルコールを多量に摂取すると肝臓での代謝機能が乱れ、中性脂肪が過剰に蓄積されてアルコール性脂肪肝(AFLD)に至ります。この状態を放置すると、アルコールの代謝によって生じる活性酸素やアセトアルデヒドなどの有害物質が肝細胞を傷つけ、炎症が起こります。これにより、肝臓が腫れたり、肝機能が低下する「アルコール性脂肪性肝炎(ASH)」へ進行します。ASHはさらに進行すると肝硬変や肝がんのリスクも高まります。
非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)
非アルコール性脂肪肝(NAFLD)は、飲酒の習慣がないにもかかわらず、過剰な糖質や脂質の摂取、肥満、運動不足などにより中性脂肪が肝臓に蓄積された状態です。この状態が続くと、脂肪が肝細胞を傷つけ、酸化ストレスや炎症を引き起こすことで、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)へ進行します。NASHでは肝細胞の壊死や肝臓の組織が硬くなる線維化が進み、放置すると肝硬変や肝がんへと発展する危険性があります。
中性脂肪とは?高いことによるリスクと改善方法を解説
悪玉(LDL)コレステロールが悪い…病院に行くべき?脂質異常症を解説!
脂肪肝の治療法は確立されている?
結論から説明すると、脂肪肝に特効薬は現状存在しません。
脂肪肝の原因の大半は、食べすぎなどの食生活の乱れ、代謝低下、糖質やアルコールの過剰摂取など生活習慣によるもののため、食事・運動・体重といった原因を改善しない限り根本的な解決になりません。
食生活や飲酒習慣を見直し、適度な運動を取り入れることで中性脂肪が蓄積されないような体質を維持することが脂肪肝の最大の予防法であり治療法にもなります。
肝臓は最も再生能力が高い臓器のひとつとされており、脂肪が蓄積しているだけの初期の脂肪肝のダメージであれば、生活習慣の改善などで元に戻せる可能性が高いです。
しかし、肝炎や肝硬変、肝がんになってしまうと、肝臓を元の状態に戻すことはできないとされているため、このフェーズでは「完治」ではなく「進行を止める」ことが治療目標になってしまいますので、脂肪肝にならないための体づくりが非常に重要です。
治験ボランティアに参加してみませんか?
医学ボランティア会JCVNは、製薬メーカーや治験実施機関から治験ボランティアの募集依頼を受け、当会に入会いただいたボランティア会員の皆さまへ、治験のご紹介とご案内をサポートさせていただくために設立された団体です。
JCVNに登録頂いた会員の皆さまには、それぞれの年齢やお住まいの地域、健康状態などによって「くすり」の治験や健康食品・化粧品モニター、医療機器の使用モニターなど多岐に渡る様々なモニター・治験・臨床研究等の案件を、主にメール配信にてご紹介しております。
登録料および利用料や年会費は一切ございません。どなた様もお気軽にご登録いただけます。
まとめ
脂肪肝は痛みなどの自覚症状が現れにくいため、気づかないところで症状が進行していることがあります。
肝臓は再生能力の高く、早期の段階であれば生活改善により肝機能を取り戻せる可能性が高いとされているので、脂肪肝の兆候や脂肪肝の原因となりうる食生活に心当たりがある場合は、早めに対処しましょう。
著者情報

JCVN編集部
JCVNでは、病気やからだに関する様々な知識をコラムとして掲載しております。
また、ご覧いただく皆さまへ分かりやすくお伝えできるコンテンツをお届け致します。
脂肪肝の基礎知識一覧
- 脂肪肝を改善する方法はある?原因から食事のポイントまで徹底解説
人気の記事
治験ボランティア登録はこちら
その他の病気の基礎知識を見る
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- PMS(月経前症候群)
- あせも
- アトピー性皮膚炎
- アルツハイマー型認知症
- アレルギー
- インフルエンザ
- ウイルス
- おたふく風邪
- がん
- クラミジア
- コレステロール
- しびれ
- とびひ
- ドライアイ
- ニキビ
- ノロウイルス
- はしか
- メタボリックシンドローム
- めまい
- リウマチ
- 不妊症
- 体重減少
- 便秘
- 前立腺肥大症
- 副鼻腔炎
- 口内炎
- 咳
- 喉の渇き
- 夏バテ
- 子宮内膜症
- 子宮外妊娠
- 子宮筋腫
- 帯状疱疹
- 心筋梗塞
- 手足口病
- 新型コロナウィルス
- 更年期障害
- 気管支喘息
- 水疱瘡
- 水虫
- 治験とは
- 熱中症
- 物忘れ
- 生活習慣病
- 疲労
- 痛風
- 糖尿病
- 耳鳴り
- 肝硬変
- 脂肪肝
- 脂質異常症(高脂血症)
- 逆流性食道炎
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)
- 関節痛
- 難聴
- 頭痛
- 頻尿
- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)
- 高中性脂肪血症
- 高尿酸血症(痛風)
- 高血圧
- 鬱病(うつ病)
こちらもよく読まれています
- 治験とは(意味やメリット・臨床試験との違い等)
- 治験の安全性 とリスク(副作用や死亡事例)
- 治験(臨床試験)参加までの流れ
- 治験モニター・ボランティアの体験談
- 病気の基礎知識
- 病気のQA
- 自己診断・健康診断
- 水虫に効く治療薬とは?おすすめの市販薬を紹介!
- 糖尿病によるめまいとは?低血糖の症状から対処法まで解説
- 逆流性食道炎の治療薬を紹介-選び方、飲む際の注意点も解説
- 糖尿病による頭痛とは?血糖値による原因から治療方法まで解説
- 骨粗鬆症(骨粗しょう症)の症状-原因や特長についても解説
- 骨粗鬆症の薬の分類と副作用を紹介!
- 頭痛薬のおすすめ5選!薬が効かないときの対応についても解説
- あせもにおすすめの薬を紹介!受診はした方が良い?予防はできる?
- 高齢者がRSウイルスに感染すると重症化する?症状や治療法、予防法について解説
- RSウイルスの対処法とは?症状から咳がひどい場合の対処法まで解説
- 便秘薬の種類・選び方を解説!おすすめ市販薬も紹介
- 口内炎におすすめの薬をトラブル別に紹介!【2024年最新版】
- 痩せる薬の種類を紹介!クリニックで処方されるダイエット薬の特徴を解説
- 治験のバイトとは?メリット・デメリットや注意点、報酬について解説