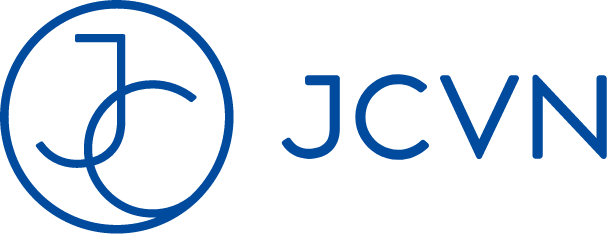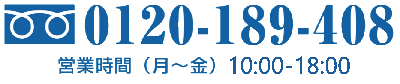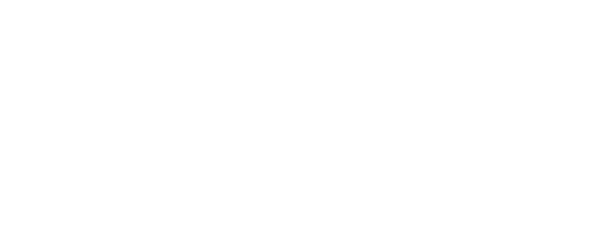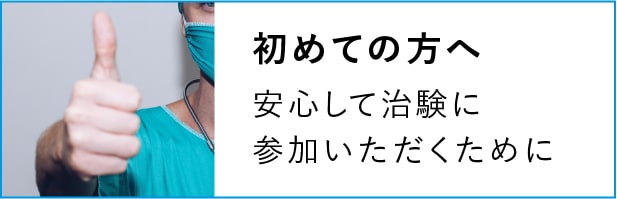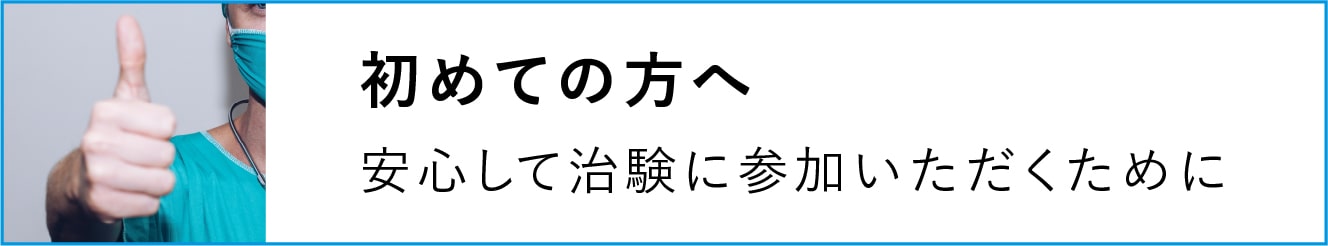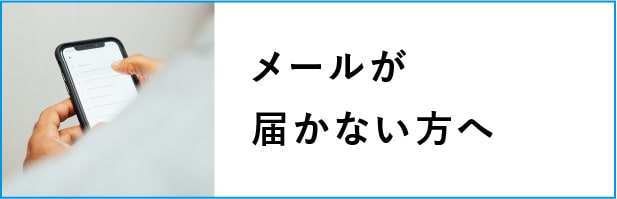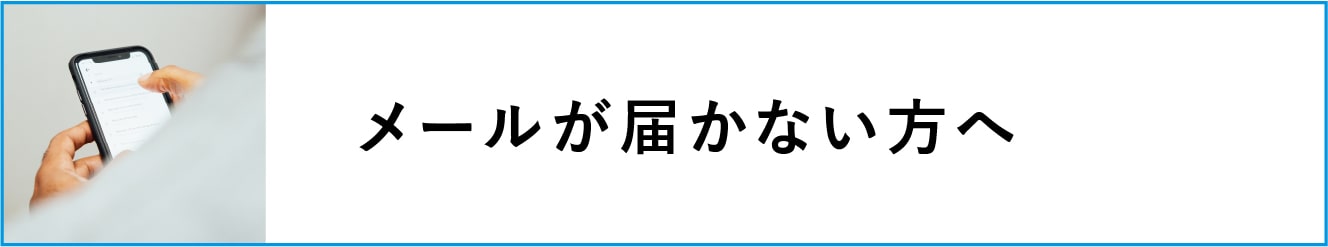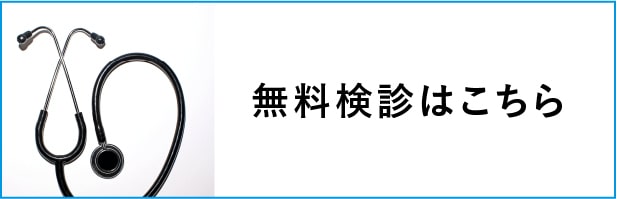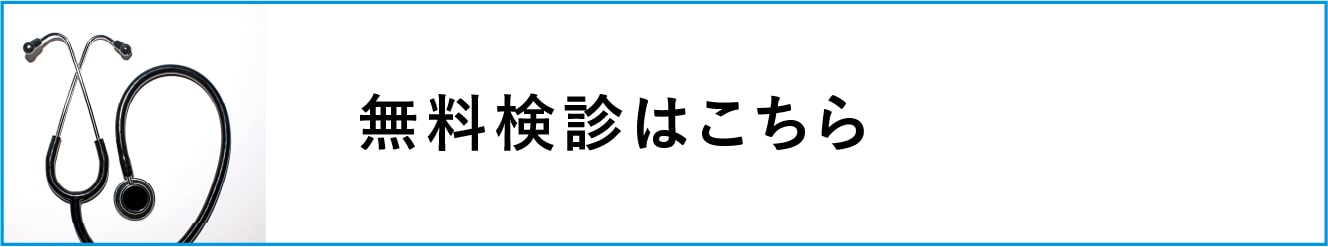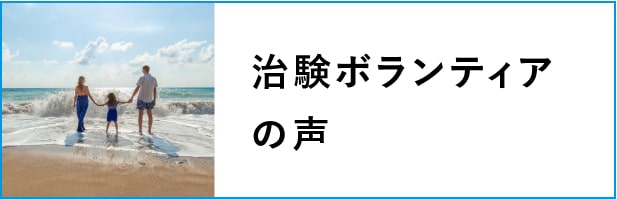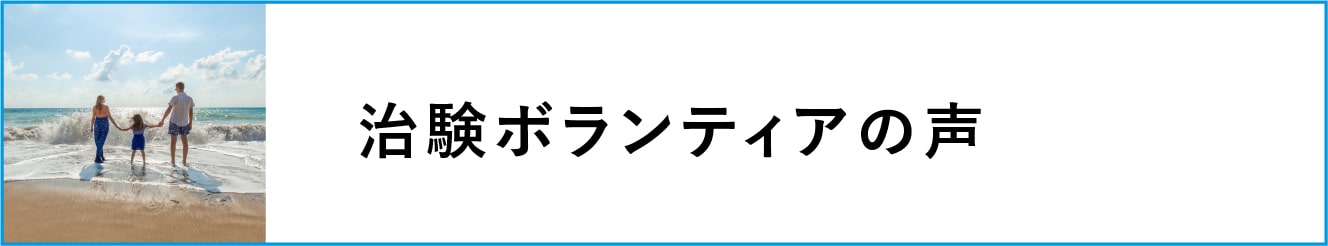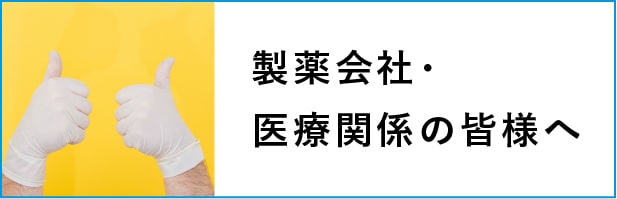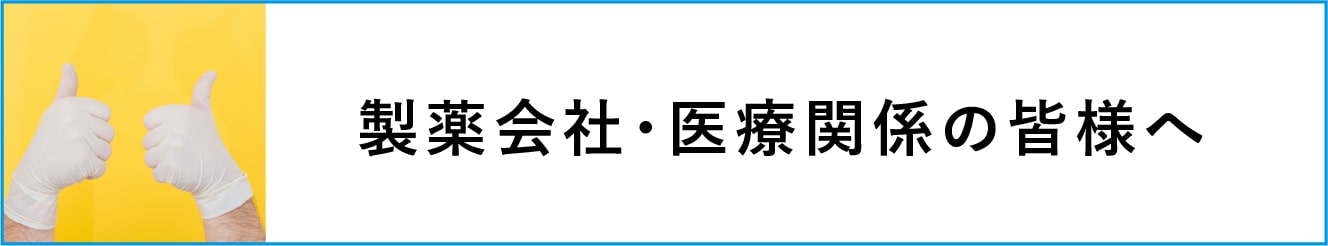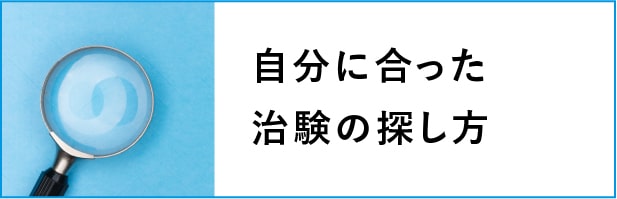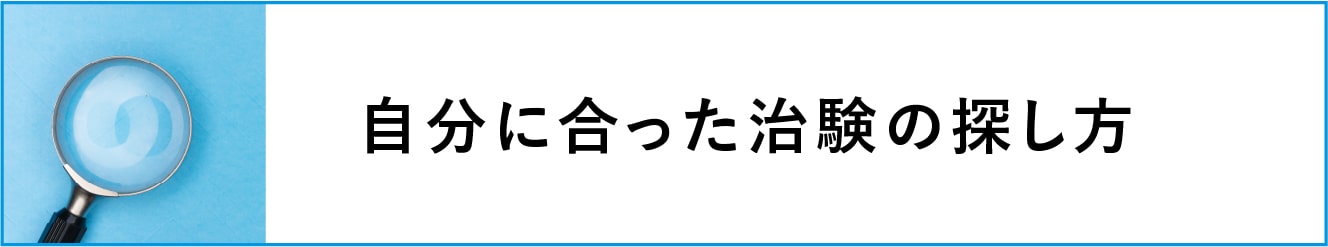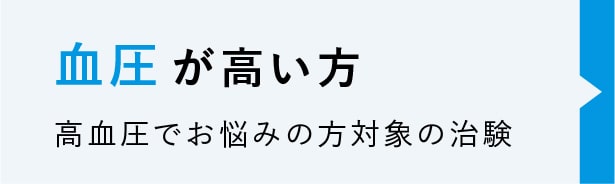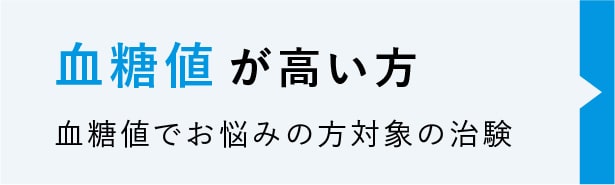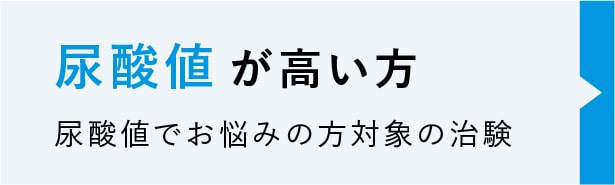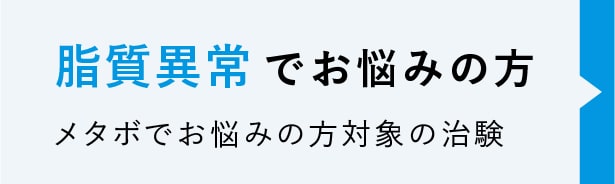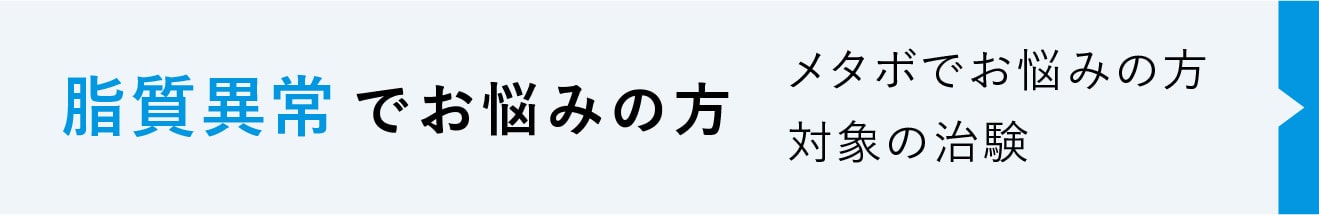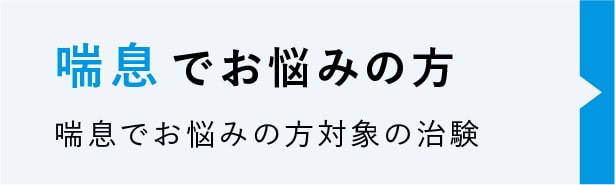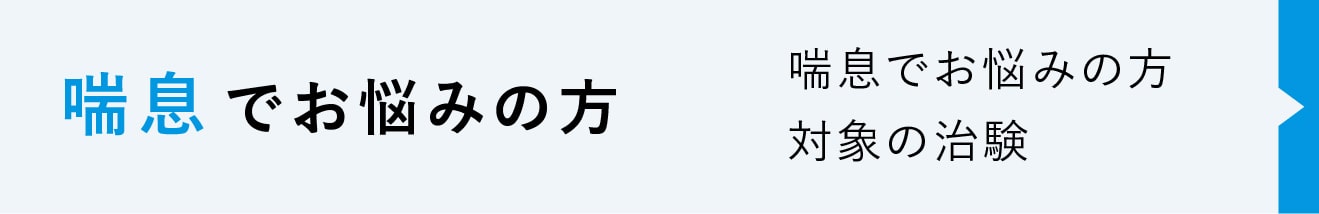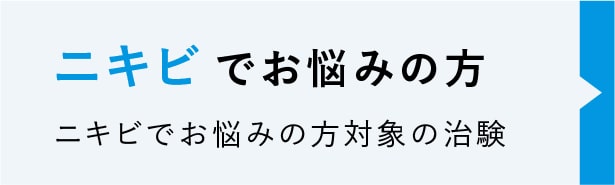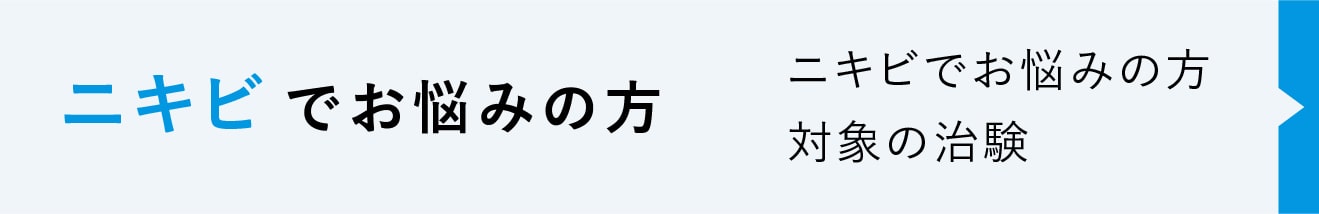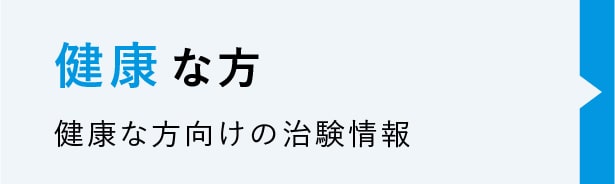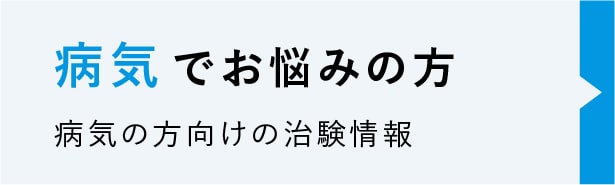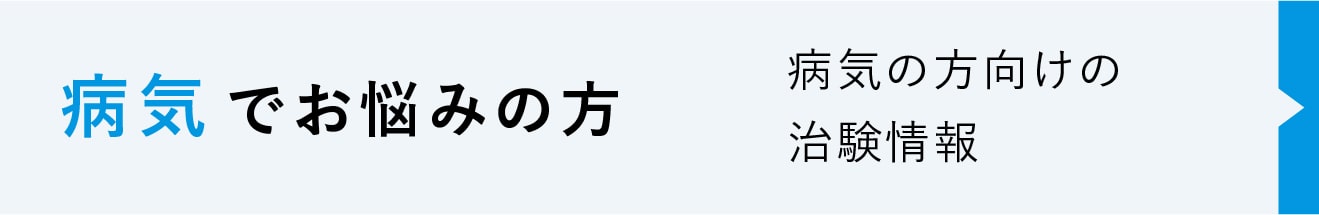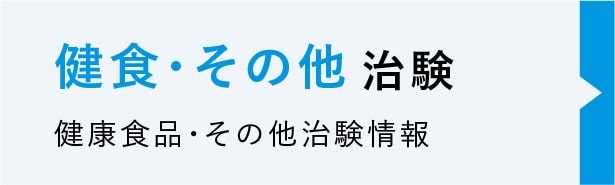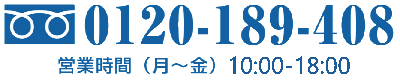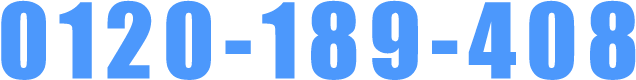【掲載日】2016/08/03 【最終更新日】2016/11/25
COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは
COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは、慢性呼吸器疾患の一つです。
死よりも恐ろしい病気としても知られおり、タバコなどが原因で肺に炎症が起こり、空気の通り道である 気道が狭くなる病気です。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)って何?
COPDは一つの病気ではありません。慢性気管支炎、肺気腫(はいきしゅ)、びまん性汎細気管支炎など、長期にわたり気道が閉塞状態になる病気の総称です。
慢性気管支炎
タンをともなった咳が特徴です。気管支に慢性の炎症やむくみ(浮腫)が生じ、タンが過剰になります。これを取り除くためにタンをともなうせきが出ます。たんの量が多くなると気管支が塞がれ、そこにウイルスや細菌が感染して、さらに炎症が広がります。進行すると気管支に空気が通らなくなり、その先の肺胞が壊れてしまいます。
肺気腫(はいきしゅ)
細気管支の先は、肺胞がぶどうの房のようについています。肺気腫はこの細胞の壁が崩れ、崩れた肺胞が大きく膨らんで弾力性や収縮性が低下する病気です。弾力性や収縮性が低下すると、息をはき出すときに肺が縮まりにくくなり、新しい空気を吸うことができないので、息切れを起こしやすくなります。
びまん性汎細気管支炎
気管支が枝分れしてだんだん細くなり、肺胞に入る手前の部分を呼吸細気管支と称しますが、この部分の慢性炎症のために咳、痰が出たり、息苦しくなる病気です。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)の原因
COPDを引き起こす最大の原因は、本人がたばこを吸うこと(喫煙)です。また他人のたばこの煙を吸わされること(受動喫煙)も発症の原因となる可能性が指摘されています。
また、肺機能は加齢とともに、低下していきます。喫煙が加わると急速に低下が進み発症すると言われています。その他、ウイルスや細菌などの感染などがあります。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)の症状
息切れやせき、タンなどの症状は、呼吸を行う臓器である肺がダメージを受け、酸素をとりいれることができないために起きてきます。
息切れ
階段や坂道を上がると息苦しくなったり、動くとつらくなったりします。
せき・タン
たばこを吸うたびに出る場合もあります。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)の検査と診断
COPDの主な原因は喫煙(タバコ)です。喫煙歴の有無は、診断には欠かせません。また、診断にあたって、以下のような検査があります。
肺機能検査
肺の働きを調べる検査です。病院で測定する精密な方法と、スパイロメーターという器具を使って測定する簡易の方法があります。
血液検査
動脈の血液中に、酸素がどの程度充足しているかを調べます。採血して酸素と二酸化炭素の分圧を調べる方法と、指にパルスオキシメーターと呼ばれる器具をつけ、酸素量のみを調べる方法があります。
胸部X線写真
合併症の有無を調べ、診断を絞り込んでいきます。
心電図
呼吸困難と心臓との関係を調べていきます。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)の基礎知識一覧
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは
人気の記事
治験ボランティア登録はこちら
その他の病気の基礎知識を見る
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- PMS(月経前症候群)
- あせも
- アトピー性皮膚炎
- アルツハイマー型認知症
- アレルギー
- インフルエンザ
- ウイルス
- おたふく風邪
- がん
- クラミジア
- コレステロール
- しびれ
- とびひ
- ドライアイ
- ニキビ
- ノロウイルス
- はしか
- メタボリックシンドローム
- めまい
- リウマチ
- 不妊症
- 体重減少
- 便秘
- 前立腺肥大症
- 副鼻腔炎
- 口内炎
- 咳
- 喉の渇き
- 夏バテ
- 子宮内膜症
- 子宮外妊娠
- 子宮筋腫
- 心筋梗塞
- 手足口病
- 新型コロナウィルス
- 更年期障害
- 気管支喘息
- 水疱瘡
- 水虫
- 熱中症
- 物忘れ
- 生活習慣病
- 疲労
- 痛風
- 糖尿病
- 耳鳴り
- 肝硬変
- 脂肪肝
- 脂質異常症(高脂血症)
- 逆流性食道炎
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)
- 関節痛
- 難聴
- 頭痛
- 頻尿
- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)
- 高中性脂肪血症
- 高尿酸血症(痛風)
- 高血圧
- 鬱病(うつ病)